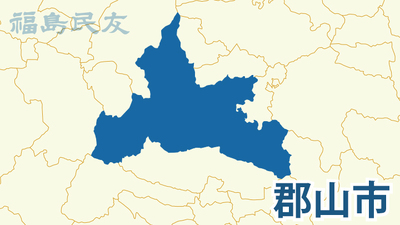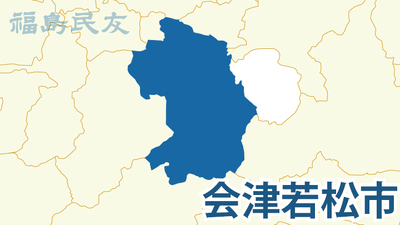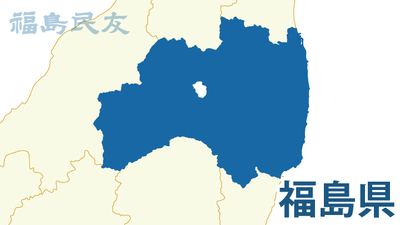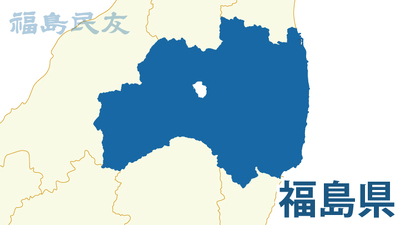安全で快適な生活を支える、生活インフラ全体の問題として考えることが大切だ。
埼玉県八潮市で発生した、県道陥没事故は、道路にトラックが転落し、約120万人に下水道の利用自粛が求められるなど大きな影響を及ぼした。下水管の腐食が原因とみられている。
下水管の老朽化の目安は50年とされているが、事故のあった場所の管は整備されてから約40年だった。県内には敷設から50年程度の管があるほか、市町村の下水を集約して処理する流域下水道には使用開始からは30年超で、建設工事着手から40年近く経過しているものがある。
八潮市の事故は決して対岸の火事ではない。県内でも同様の大規模事故の起きる恐れがあるのは否めない。下水道のほか、道路や橋、上水道など老朽化が進んでいる生活インフラを適切に管理、維持していくための方策を強化する契機としなければならない。
国土交通省は設備の更新などに今後の30年で150兆円超の費用が必要となるとの試算を示している。本県は首都圏などより下水道整備が遅かったものの、今後は先行する県外の自治体と同様、更新を進めていかなければならないことに変わりはない。
下水道事業を支えるのは、住民や市町村が支払う利用料だが、人口減少が進むことで住民の支払う使用料は減り、自治体の財政も余裕はさらになくなっていくと見込まれる。しかし、更新などの費用が減ることはない。
国交省が自治体に推奨しているのは、設備の更新の優先順位付けを徹底することだ。八潮市の事故の原因とみられる管が整備から50年に達していなかったように、下水管は設置する場所の地質や流量などにより老朽化の進み具合に差が生じることが分かっている。検査などを通じて、管の更新や長寿命化を施す必要がある部分などを的確に見極めることが、費用の抑制につながる。
設備の更新などを担う民間業者の確保も重要だ。計画的に更新を進めていくことで、それを請け負う工事業者の経営を安定させていく必要がある。
石破茂首相は八潮市の事故を受けて、国交省に対し、下水道を含めた生活インフラ全体の老朽化対策を検討するよう指示した。下水道に限らず、生活インフラの老朽化は今後の国民の生活を守る上で避けて通れない課題だ。国が財政面を含め、市町村のインフラ維持に向けた動きをどう促していくのかが問われる。