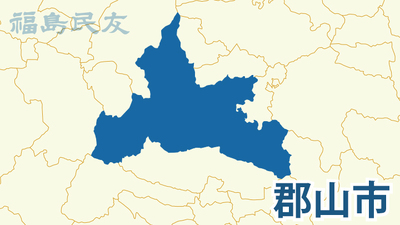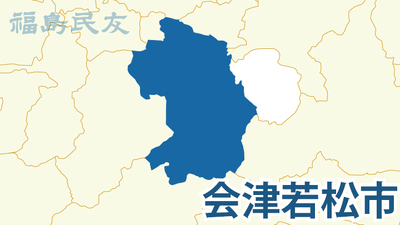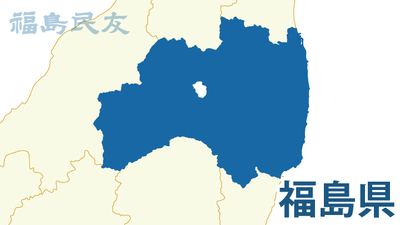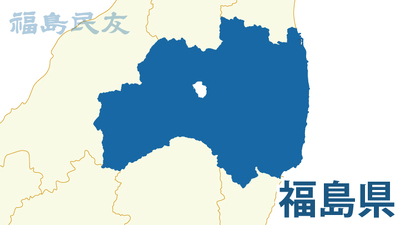原発事故時に自宅や病院、高齢者施設などにとどまる屋内退避は被ばくを抑えつつ、準備不足のまま避難することによる関連死を防ぐのに有効だ。万一の際、住民らが避難行動の選択肢の一つに加え、的確に対応できるよう平時から課題を取り除く必要がある。
原子力規制委員会の検討チームが、屋内退避に関する報告書案をまとめた。食料や水の備蓄量などを参考に、退避期間の目安を3日間とした。食料調達や介護など生活維持のための一時的な外出は可能とすることが盛り込まれた。
原発事故時の住民避難や被ばく防護策をまとめた国の原子力災害対策指針には、空間放射線量を踏まえた避難の実施などが定められている。一方、屋内退避の期間や避難に切り替える判断基準などはなかったため、効果的な運用方法の検討が進められてきた。
報告書案は3日たった後も、自治体からの物資供給や人的支援、放射性物質の拡散状況などを踏まえ、生活の維持が可能であれば屋内退避を継続することを基本とした。生活維持が困難であれば遠方への避難に切り替える。
東京電力福島第1原発事故では、被ばくを避けるため、物資の輸送を担う業者が原発周辺の地域に入らなった。多くの住民が一斉に避難し、交通網は混乱した。報告書案の想定のように、整然と屋内退避が行われるかは疑問だ。
検討チームメンバーの坪倉正治福島医大教授は会合で「屋内退避から避難に変わるときの時間がなく、患者を無理やり動かして亡くなったような教訓が福島にはたくさんある」と語った。その上で、実際に屋内退避や次の段階の避難への切り替えなどができるのか、関係者と事前にすり合わせることの重要性を指摘した。
報告書をまとめて終わりではない。規制委には関係省庁と連携し、自治体や住民らが実態に即した対策を立てられるよう、支援することが求められる。
志賀原発のある能登半島では昨年1月、地震による家屋倒壊や道路寸断が多発した。報告書案は複合災害への対応について、地震や津波など自然災害対策との連携強化が極めて重要とした。ただ、自宅が倒壊した際の屋内退避場所となる指定避難所の耐震化、災害に強い避難経路の整備などが必要と指摘するにとどめている。
自然災害対策は規制委の所管外なのは理解できるが、議論されているのは原発周辺の地域の課題だ。再稼働を進める政府が防災対策の強化に着実に取り組むよう、規制委は注文を付けてほしい。