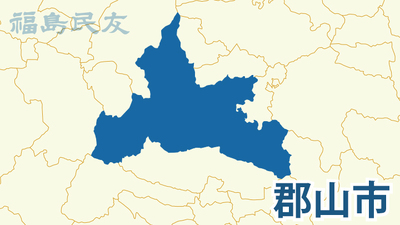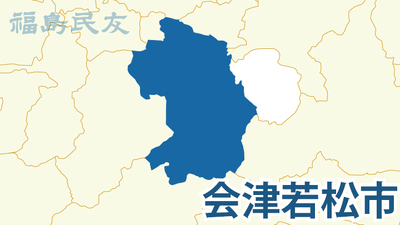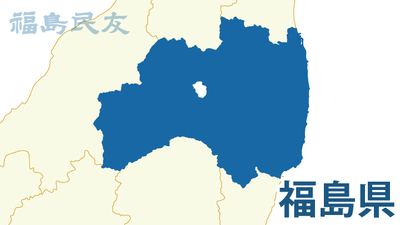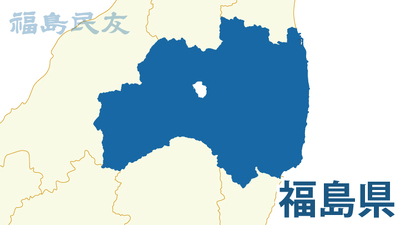空気が乾燥し、強風が吹くこの時期は、大きな被害を招く恐れがある。防火の意識を高め、火の扱いに細心の注意を払いたい。
岩手県大船渡市で26日に発生した山林火災は焼失面積が1200ヘクタールを超え、鎮火の見通しが立っていない。点在する集落に火が広がり、住宅など80棟以上に延焼したほか、現場付近で1人の遺体も見つかった。3千人以上に避難指示が出されるなど事態は深刻だ。
例年、林野火災は3~5月に多く発生している。県によると、昨年1年間で発生した51件の林野火災のうち、31件は3~5月に起きた。枯れ草や枯れ木を焼いた際の不注意や、たばこの不始末など、出火原因は人為的なものが多い。
車両が入りにくい山林での消火活動は水の確保が難しく、急斜面や樹木などが障害となり、ホースの連結なども容易ではない。風向きなどで状況が一変するため、活動そのものが極めて危険だ。
最初は小さな火でも気象条件などで瞬く間に広がり、手に負えなくなるのが林野火災の怖さだ。県内でも浜通りや中通りは空気が乾燥した状態が続いている。山の中に入ったときは当然ながら、農作業でも山林などに近い田畑では火を使わないことを徹底すべきだ。
県内では昨年、24人が住宅火災で犠牲になった。消防庁の統計によると、全国の住宅火災は2021年から増加傾向にあり、23年の死者数は1千人を超えた。約半数は気付くのに遅れて逃げ道がない、体が不自由で動けない―などの逃げ遅れが原因とみられ、犠牲者の7割が65歳以上の高齢者だ。
大きなブザー音で出火を知らせる住宅用火災警報器の設置が、早期発見や逃げ遅れの防止のための数少ない対策の一つだ。早く気付き、出火から間もない段階であれば、消火器などによる初期消火で鎮火できる可能性もある。
警報器は全ての住宅に設置が義務付けられているものの、県内の設置率は8割にとどまる。未設置の場合はホームセンターで購入するなど備えを急いでほしい。
高齢者だけの世帯では警報器を設置していても交換の目安の10年を過ぎているものや、電池が切れた状態で放置しているケースがあるという。離れて暮らしていても家族などが時折、警報器の状況や電池を確認することが大切だ。
きょうから7日まで春の全国火災予防運動だ。ストーブなどの周りに燃えやすいものを置かない、火のそばから離れない、電気コンセントを清掃する―など、日ごろからできる備えを実践し、大切な命と財産を守る必要がある。