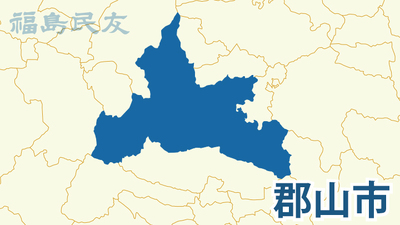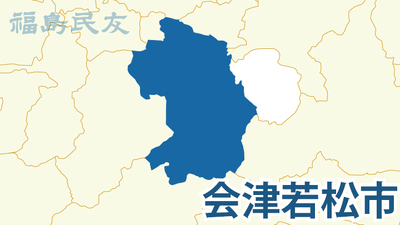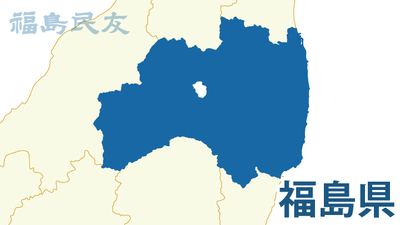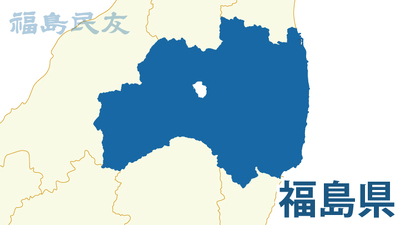東京電力福島第1原発事故で被災した相双地方で、サツマイモの作付面積が拡大している。サツマイモは近年、焼き芋人気の高まりやスイーツの材料としての利活用などで市場の注目度が上がっており、生産者の所得向上などが期待されている。
浜通りでは以前、サツマイモの栽培は、農家の自家消費用や家庭菜園などにとどまっていた。しかし、原発事故からの営農再開への取り組みを進めていくなか、機械化により作業の手間が比較的かからず、土地を選ばず順調に生育する特長などが着目され、新たな園芸作物として、楢葉町を中心に栽培が始まった。
生産者は年々増え、JA内に生産部会が設立された。近年では楢葉町の周辺の富岡町、大熊町、浪江町、南相馬市などでも作付けが始まっている。県によると、原発事故前にほぼゼロだった作付面積は、2023年産で県全体の作付面積の4割強を占める約70ヘクタールに達している。
気候の変化や寒さに強い品種の開発などにより、かつては茨城県以南とされていたサツマイモの適地は拡大しているものの、県のさまざまな農業関係の計画では、サツマイモの振興は明示されていない。県は、相双地方を本県のサツマイモ栽培の拠点として位置づけ、高まっているサツマイモ需要を取り込む新興産地として育成していくことが重要だ。
相双地方のサツマイモの多くは、主に加工用として販売されている。生産者が集中している楢葉町では現在、加工用に加えて一般の市場に流通させるサツマイモの量を増やすことを目指しているほか、町で設置した特産品開発のための施設を使った干し芋の生産などにも取り組んでいる。
加工用や野菜としての流通など多様な市場のニーズに対応するには、生産者の増加に加え、個々の農家の収量増加や生産するサツマイモの品質向上を図っていくことが避けられない。県や市町村、生産団体には、産地としての競争力を強化するため、連携した営農指導を進めるとともに、付加価値を高める6次化の動きを後押しすることを求めたい。
相双地方のサツマイモを巡っては、浜通りの高校などがスイーツづくりや商品開発を通じて生産現場と交流する動きが出ている。県や市町村には、サツマイモによる相双地方の営農再開や栽培面積の規模拡大を通して、原発事故で一度は希薄になった学校の児童生徒と生産者の関係の再構築にもつながっていくよう心がけてほしい。