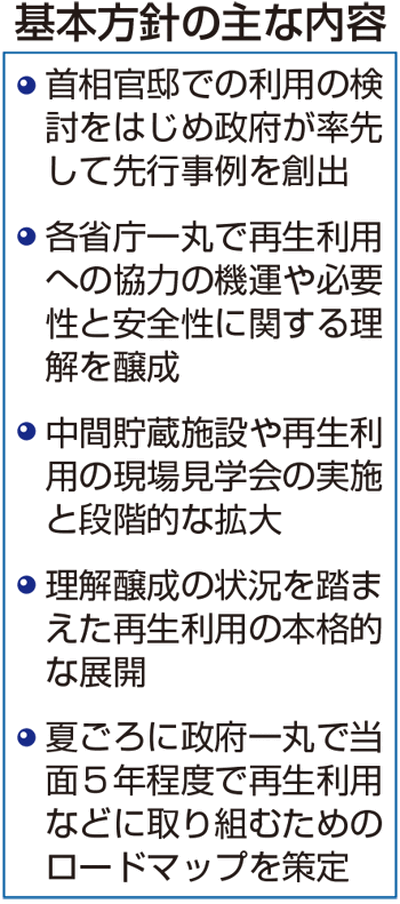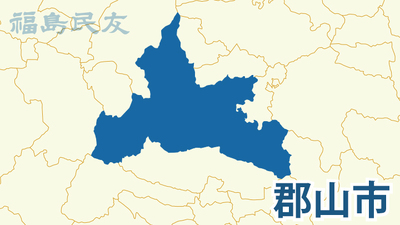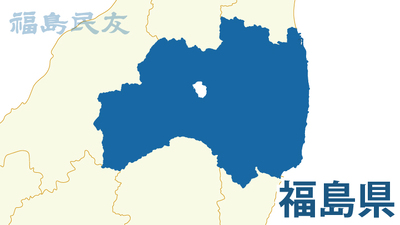東京電力福島第1原発事故に伴う除染土壌の再生利用を巡り、政府が率先して事例創出に取り組むことなどを盛り込んだ基本方針が27日に決定された。実施予定地の周辺では賛否の声が聞かれ、本県関係者からは理解醸成の効果や再生利用本格化の実現性を疑問視する見方もあった。
政府が先行事業の予定地と明言した首相官邸。建物を囲むように植栽があり、敷地への立ち入りは厳重に管理されている。周辺の通行は官僚が多い一方、この日は修学旅行生の団体や一般市民の姿も見られた。
近くを歩いていた東京都北区の自営業の男性(65)は「どういう土をどのように使うのか分からず、現時点では非常に危険性を感じる」と懸念。「実施するなら飛散や流出を防ぐ対策を徹底してほしい。国の放射線管理は信頼性に欠ける印象が強い」と批判混じりに語った。
夫婦で観光で訪れた大阪府の無職の女性(67)は「再生利用のことは知らなかった。福島の復興に必要なら、進めてもいいと思う」と話す。その上で「ただ、今後もし自分の家の近くが候補地になったらと思うと考えてしまう。孫たちも関わってくるので」と複雑な胸中をにじませた。
環境省は2017~24年度、再生利用の実証事業を飯舘村など県内3カ所で実施した。この結果、周辺住民が追加で受ける放射線量は国際基準の年間1ミリシーベルトを下回り、十分に安全を確保できることを確認している。
しかし、県外で計画した東京都新宿区など3カ所での実証事業は住民から強い反発を受け、いずれも頓挫した。環境省の昨年度調査では、再生利用を安全だと考える県外在住者の割合はわずか15.9%で、実現を阻む壁になっている。
政府は昨年12月に〈1〉再生利用の推進〈2〉理解醸成〈3〉県外最終処分への取り組み―の3本柱を掲げた。基本方針で各項目の具体化が期待されたが、目新しい話題は再生利用に関してのみ。27日の記者会見で、先行事業の箇所数や規模などを問われた担当者は「今後検討する」と繰り返した。
地権者「理解醸成にならない」
中間貯蔵施設の地権者会長を務める門馬好春さん(68)は「今回の基本方針は時間軸を含め、県外最終処分の実現に向けた具体的な道筋が全く見えない。期待はずれの内容だ」と指摘。「一般市民が立ち入れない場所で再生利用しても(政府が目指す)理解醸成にはつながらないのではないか」と疑問を呈した。
最終処分の法定期限は、2045年3月。門馬さんは「あと20年しかない。地元の声を受け止め、約束は必ず守ってほしい」と訴えた。