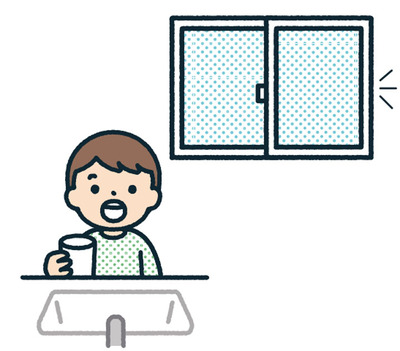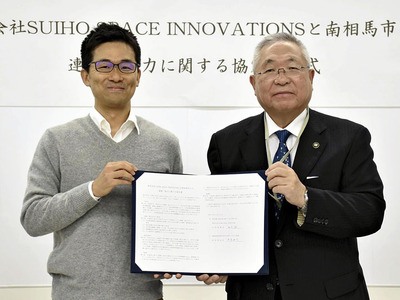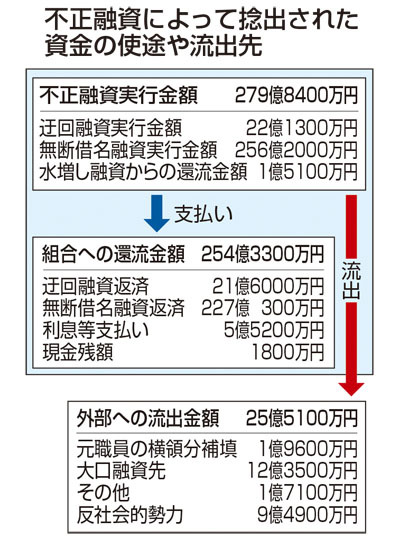原発事故をきっかけに、「放射線」という言葉が私たちの暮らしの中で強く意識されるようになりました。福島県では2011年度から、放射線について学ぶ授業が本格的に導入され、小中学校で独自の教材を用いた教育が始まりました。 前回まで見てきたように、広島や長崎では「平和教育」の一環として被爆の記憶を学ぶ授業が中心であり、青森では原子燃料サイクル施設を背景に「科学技術としての理解」が重視されています。それぞ...
この記事は会員専用記事です
残り460文字(全文660文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。