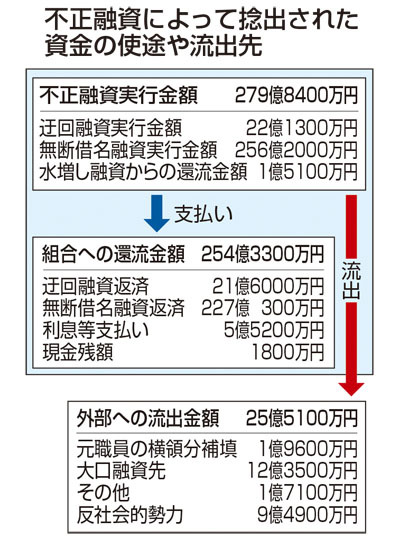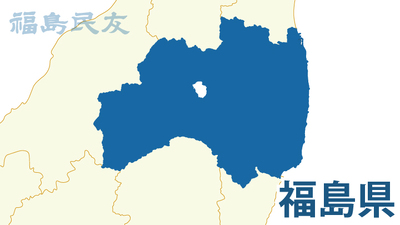今回はスポーツをする際や体を動かす作業をする際の熱中症の特徴と予防法について、厚生労働省、環境省などの記事を参考にお話しします。
1.熱中症の重症度分類
重症度により、1度(軽症)、2度(中等症)、3度(重症)、4度(最重症)に分類されます。
【1度(軽症)】 立ちくらみ、目まい、筋肉のこむら返り(筋けいれん)などの症状
【2度(中等症)】 頭痛、吐き気、嘔吐(おうと)、倦怠(けんたい)感、虚脱感などの明らかにいつもと違う症状
【3度(重症)】 呼びかけに反応しない意識障害、けいれん、手足の運動障害などの症状
【4度(最重症:新設)】 深部体温が40度を超える、意思疎通ができない重い意識障害
それぞれの重症度とその対応については左ページの図に示しました。特に最重症例では、全身に水や氷水をかけたり、その後体をタオルなどで覆ったりするなどの処置が必要になります。
2.スポーツにおける熱中症の条件
熱中症を起こす条件は、以前にお話ししたように環境、個人、行動・運動の条件になります。
【環境】気温、湿度が高いほど、直射日光や輻射熱が大きいほど、起こりやすくなります。また、風が無い時、前日に比べ気温や湿度が急に上昇した際も熱中症が起こりやすくなるので注意が必要です。
【個人】肥満の人、体力が低い人、暑さに慣れていない人、体調の悪い人は熱中症になりやすくなります。また、学校管理下での熱中症死亡事故の70%が肥満者であり、肥満の方は注意が必要です。
【運動】激しい運動ほど熱中症を起こしやすくなります。屋外では野球、ラグビー、サッカー、屋内では剣道、柔道で多く発生しています。また、半分以上は持久走やダッシュの繰り返し等のランニングの際に起きています。ランニングは短時間(30分以内)でも熱中症死亡事故が起きています。暑い時期のランニングは特に注意が必要です。
3.スポーツにおける熱中症予防の原則5カ条
【1】環境条件を把握し、それに応じた運動、水分補給を行い、休憩を取る
暑い時期は運動時間より休憩時間を長く取る。2時間以上の持続的な運動やスポーツは避ける。
【2】暑さに徐々に慣らしていく
最低でも1週間程度かけて、少しずつ、運動強度をあげていく。
【3】個人の条件を考慮する
各自のペースで運動強度を変える。
【4】服装に気を付ける
軽装で吸湿性や通気の良い素材を選ぶ。屋外のスポーツの際には帽子をかぶり、できるだけ薄着にするように努める。
【5】具合が悪くなった場合には、早めに運動を中止して、必要な処置をする
吐き気や嘔吐があり、自分で水分が取れない場合には、医療機関へ搬送して点滴などの治療が必要。保護者や指導者は、常にスポーツに参加している選手の健康観察を行い、異常が見られたら速やかに必要な措置を取る。
4.屋外での作業時の熱中症
屋外で熱中症になりやすい職業は、建設業、製造業、運送業、警備業などです。事業主は作業開始前にチェックシートを用いて、熱中症予防に努めなければなりません。
① 当日の作業、運動量などの強度の確認
② 温度条件の確認(気温、湿度、WBGT指数計で測定して、暑さ指数を出すなど)
③ 涼しい場所(休息場所・救急対応)の確保
④ 涼しい場所で、体を冷やす用意(水、タオル、うちわ、クーラー)はあるか。作業場に水風呂、シャワーの用意があるか
⑤ ふさわしい着衣、体を冷やす工夫は十分か
⑥ 作業中の休憩、飲水は確保できるか
⑦ 前日までの行動確認、寝不足や疲れがないか、深酒をしていないか、朝食は食べたか
⑧ 当日、体調不良ではないか。作業場での体温計の準備
⑨ 近隣の医療機関と搬送体制の確保
最近はウェアラブル端末で体調の見える化を導入している企業もあります。
◆ ◆ ◆佐藤先生の「健康ジャーナル」は今回で最終回となります。ご愛読いただき、ありがとうございました。