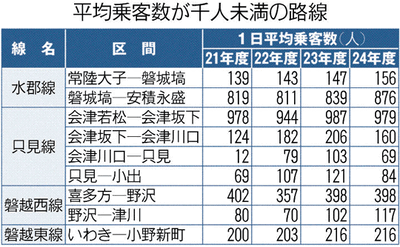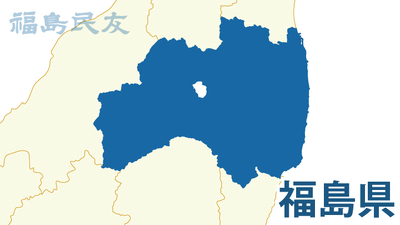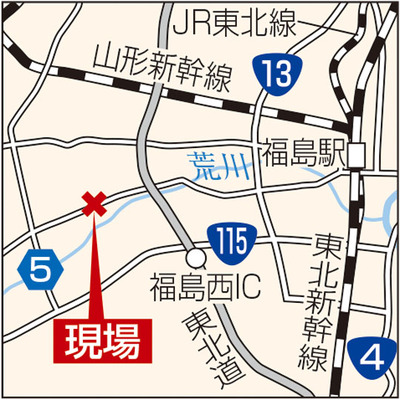会津若松市の鶴ケ城天守閣が再建されてから17日で60周年を迎えた。戊辰戦争で籠城戦の末に会津藩が敗れ、傷ついた城が取り壊されたのは1874(明治7)年。石垣だけ残った約90年の時を経て、60年前に復活した城は多くの県民が心を寄せる会津のシンボルだ。本県観光の核として国内外の人々を魅了する中、増え続けるインバウンド(訪日客)や景観保全への対応が求められている。
天守閣への入場者数は、新型コロナウイルス感染症による急速な落ち込みから回復し続けている。近年、底上げしているのは訪日客で、昨年度は過去最多となる3万2970人の訪日客が訪れ、2019年度の約1.3倍となった。今年4~8月の入場者数は1万274人で昨年度を上回るペースで推移しており、国籍別では台湾から訪れる人たちが大半を占めている。
訪日客が増加する中、英語など多言語による案内が課題となっている。一般財団法人会津若松観光ビューロー天守閣管理課の芥川航大さん(22)は「翻訳アプリなどで対応するなどしていたが、追い付かない状況」と話す。
同法人は昨年度から本年度にかけ、外国籍の派遣社員2人を採用したり、多言語の案内板を増やすなどの対応を続ける。
土塁や石垣
保全課題 天守閣を中心とした一帯は公園で、千本桜として知られる桜の木の樹勢の回復のほか、土塁や石垣の保全も今後の課題となりそうだ。このうち植樹から100年以上が経過する桜の木については、本年度から維持に向けて本格的な追肥作業が始まった。
現在は会津若松観光ビューローのほかに、NPO法人会津鶴ケ城を守る会も景観保全に向けて活動している。同法人は今年に入り、二の丸周辺約7400平方メートルの土手や土塁の草を刈り、倒木の撤去に取り組んだ。同NPO副理事長の石田明夫さん(68)は「生い茂る草木は土塁や石垣の崩れる原因にもなる。草木で見えなくなってきているのでメンテナンスが必要だろう」と指摘する。