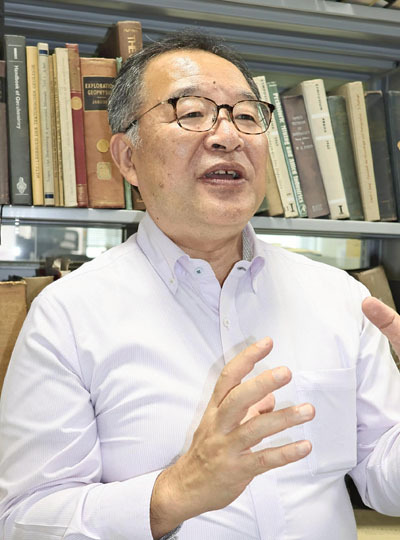「以前からできるできると言いながら、いまだ具体的に目に見える形になっていない」。浪江町から二本松市の仮設住宅に避難する天野茂さん(80)はいら立ちを見せながら話す。指摘するのは、原発事故で全町避難とともに叫ばれた「仮の町」が、その後、復興政策の中でほとんど語られることがなくなった点だ。避難先の自治体の中に、さまざまな機能を備えた避難自治体の集落を造る構想は、消えてしまったのか。 小規模化で"絆"...
この記事は会員専用記事です
残り1,250文字(全文1,450文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。