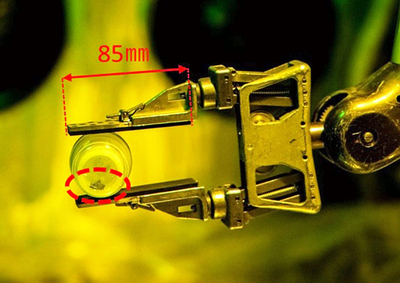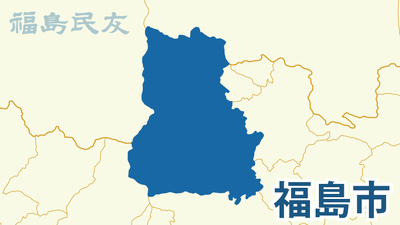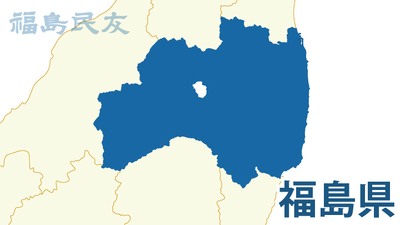被災の経験から教訓を学び、伝え、次に備えることでつくり上げる「災害文化」。命を守る行動、地域の防災や減災をもたらすこの文化をどう育んでいくのか。本県では東日本大震災と東京電力福島第1原発事故後、被害の大きさや教訓などを伝える施設が数多く建設された。県内外からの視察研修や教育旅行などによって活用され、風化を防ぐ一助となっている。
■東日本大震災・ 原子力災害伝承館(双葉町)
地震、津波、原発事故に伴う複合災害の実態や、復興への歩みを紹介している。被災住民による語り部講話は1日4回行われている。
震災の記録と教訓を継承する拠点として2020年9月に開館した。館内は震災・原発事故を時系列に沿って伝える六つのゾーンで構成され、震災当時の福島民友新聞の紙面なども展示している。震災や原子力災害に関する図書、各自治体の震災記録誌などをそろえた資料閲覧室もある。
3月下旬まで企画展「長期避難と祭り~伝統文化がつなぐ地域住民の絆」を開催。2月22、23日には双葉郡の民俗芸能団体の披露会を予定している。
■いわき震災伝承みらい館(いわき市)
 展示されている「奇跡のピアノ」(手前)と寄せ書き入りの黒板=いわき震災伝承みらい館
展示されている「奇跡のピアノ」(手前)と寄せ書き入りの黒板=いわき震災伝承みらい館
震災の記憶や教訓を後世に伝えようと、2020年5月に開館した。館内にはいわき市の豊間中で津波被害に遭った後、修復された「奇跡のピアノ」や同校の当時の生徒の寄せ書き入り黒板などが展示されている。地震や津波、原発事故、復旧・復興の歩みなどをまとめたパネル展示、津波の映像の放映も行っている。
震災を経験していない世代にも関心を持ってもらおうと企画展を開催している。高田悟館長(63)は「災害はいつ起こるか予測できないからこそ、教訓を伝えていく必要がある。新しい展示を増やす工夫をして何度も来てもらえるような施設にしたい」と話す。
■とみおかアーカイブ・ミュージアム(富岡町)
 富岡町の歴史や震災をたどる資料を展示している=とみおかアーカイブ・ミュージアム
富岡町の歴史や震災をたどる資料を展示している=とみおかアーカイブ・ミュージアム
富岡町が役場近くに整備した博物館で2021年7月に開館。「複合災害を地域の歴史に位置づける」をテーマに、町の地域資料や震災・原発事故による震災遺産を収蔵・展示している。
常設展示室には資料約430点が並ぶ。前半は富岡の成り立ちや特徴などをテーマ別に解説している。後半は震災遺産を中心に構成し、地震や津波による被災や役場の災害対応、避難生活などについて、津波で被災したパトカーなど現物資料の展示を通して紹介している。
同ミュージアムの門馬健専門学芸員は「地域で長い時間をかけて積み重ねられてきた日常が、覚悟なく奪われた事実を町・町民の目線で伝え、『あの日』を境に起きた地域の変化を紹介していきたい」とした。
■県環境創造センター交流棟(コミュタン福島)(三春町)
 展示物を刷新し、環境についてより視覚的に学べる展示内容となった=コミュタン福島
展示物を刷新し、環境についてより視覚的に学べる展示内容となった=コミュタン福島
2016年にオープンした。放射線や本県の環境、震災以降の復興の歩みを学べる施設として県内をはじめ全国から来館者が訪れる。
23年に展示物を刷新し、環境についてより視覚的に学べる展示内容となった。原発事故で飛散した放射性物質の状況や、地球規模の環境の現状を投影する「マッピングふくしま」、再生可能エネルギーと地形との関係を砂場で学ぶ「エネルギークリエーター」のコーナーなどを新たに設けた。佐々木正広総務企画部長は「放射線などの情報を正確に発信してきた。今後も、震災の記憶がない子どもたちに福島で起きたことを伝え、一緒に未来を考えていきたい」と話す。
■相馬市 伝承鎮魂祈念館(相馬市)
 震災直後の状況を伝えるパネル写真=相馬市伝承鎮魂祈念館
震災直後の状況を伝えるパネル写真=相馬市伝承鎮魂祈念館
震災で失われた相馬の原風景を後世に残し、災害の教訓を広く伝えようと、津波で壊滅的な被害を受けた相馬市原釜地区に整備され、2015年4月に開所した。
玄関を入った正面のホールには、市内で震災の犠牲になった458人の名前を掲げる。展示は主に「原風景」と「被災」の二つに分かれる。原風景コーナーでは、震災前の原釜地区などの様子を写真で紹介する。被災コーナーでは、震災直後の様子、救助活動などを記録した写真、新聞記事で当時を振り返る。
施設を管理する市商工観光課の渡辺宏子さん(48)は「映像もあり、津波のすさまじさを実感できるようになっている。震災の記憶を風化させず、伝えていきたい」と話した。