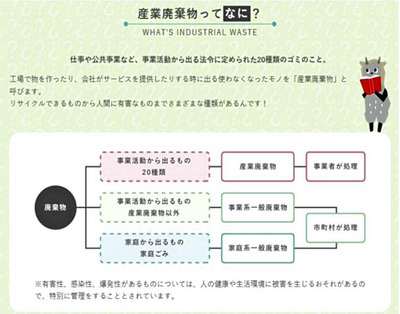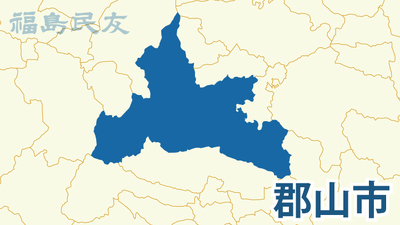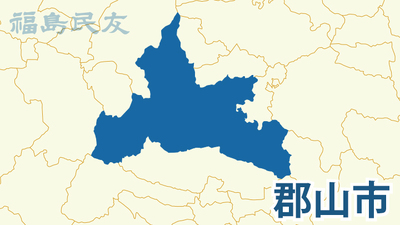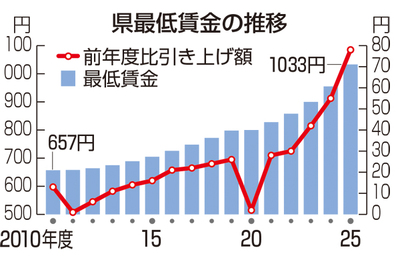福島医大糖尿病内分泌代謝内科学講座の田辺隼人准教授、島袋充生主任教授らの研究チームは、糖尿病の人の将来の筋力低下リスクを、「尿中タイチン」というたんぱく質の濃度を調べることで予測できることを明らかにした。リスク予想に関する信頼性の高い指標はこれまで存在しなかったが、簡単な尿検査によって筋力低下の兆しが数年前から捉えられるようになり、一人一人に合った予防や治療につなげられるという。
研究チームは医大と徳島大、神戸大で構成。筋損傷が生じると血液中に放出され尿中に排出される「尿中タイチン」が、加齢などによって筋肉量や身体機能が低下し、フレイル(虚弱)や要介護状態を招く「サルコペニア」の発症を予測する指標であることを世界で初めて明らかにした。
研究では2型糖尿病でサルコペニアのない444人(平均年齢66歳)を対象に、尿中タイチン濃度とサルコペニア発症との因果関係を追跡調査した。その結果1年後から、尿中タイチン濃度が高い人ほどサルコペニアを発症しやすい傾向が現れた。特に握力の低下と関連することも分かった。
サルコペニアは進行すると寝たきりになったり、他の病気につながったりする病気。2016年に疾病に認定されてから、いかに早く発見して予防や治療をしていくかの方法が世界中で模索されている。一方、サルコペニアは骨格筋量や握力、歩行速度を測って判定するが、診断の難しさも指摘されているという。
糖尿病の人はサルコペニアが進行しやすいことが知られているが、発症を早期に予測できる信頼性の高い指標はなかった。研究で尿中タイチンが指標になることが分かり、数年後のリスク予測も含め明確に診断できるようになるという。
研究成果は8月25日付で、米国糖尿病学会が発行する糖尿病内分泌分野のトップジャーナル「ダイアベティス・ケア」に掲載された。