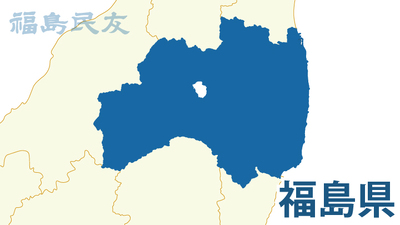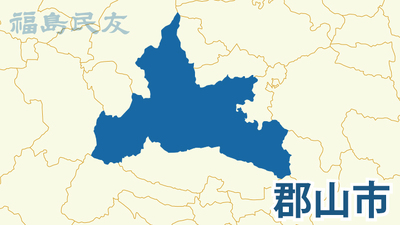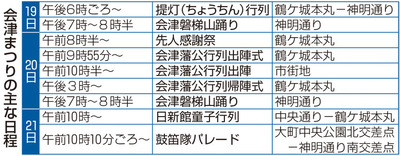福島医大医学部放射線健康管理学講座の坪倉正治教授(43)らの研究グループは、新型コロナウイルスワクチン接種者の「IgG抗体」の変動を解析し、ワクチン接種後に感染する「ブレイクスルー感染」のリスクが高い特徴の集団があることを明らかにした。継続的な接種を優先すべき人が分かるようになり、感染リスクの低減につながることが期待されるという。
IgG抗体は、ウイルス表面のたんぱく質に結合し、ウイルスの働きを抑える。坪倉氏らは名古屋大などとの共同研究で、県民2526人を対象に追加接種後の血中IgG抗体の動態を解析した。
その結果、抗体が長期間維持される「耐久型」、抗体の誘導が不十分で速やかに減衰する「脆弱(ぜいじゃく)型」、初期には抗体が高く誘導されるが、その後急速に減少する「急速低下型」―という三つの特徴的な集団があることが判明。このうち「脆弱型」と「急速低下型」の人は、早い段階でブレイクスルー感染を経験していることが分かった。
また、ブレイクスルー感染を経験した群としなかった群を比べる形で、複数の抗体の量を調べると、IgG抗体などに有意な差はなかった一方、主に鼻や喉などの粘膜で働く「IgA抗体」の血中の量に差が見られた。感染群は追加接種後100日以内のIgA抗体が有意に低かった。このため、IgA抗体がブレイクスルー感染リスクの高い人を予測する指標になり得るという。
研究成果は18日付で国際学術雑誌「サイエンス・トランズレイショナル・メディスン」に掲載された。この成果を用いることで感染の高リスク集団を早期に特定できるようになれば、より適切なタイミングでの継続的な接種が可能になるという。