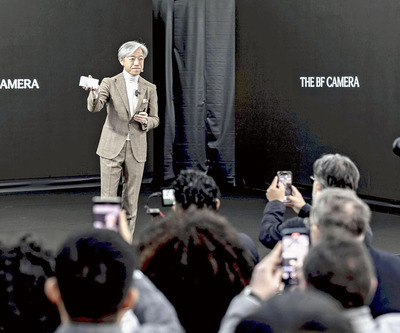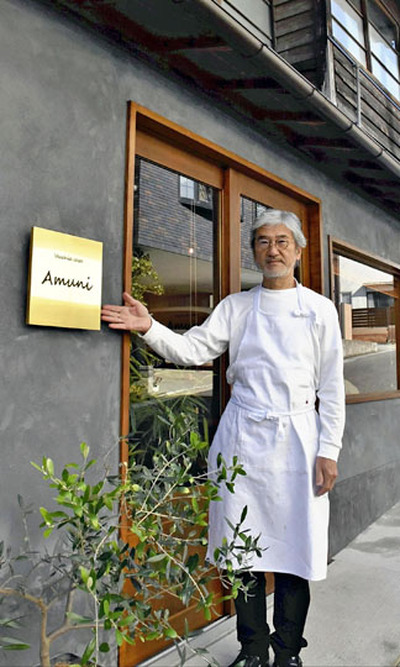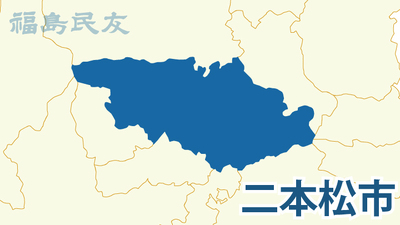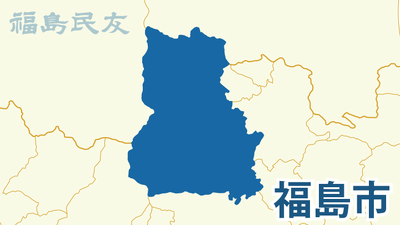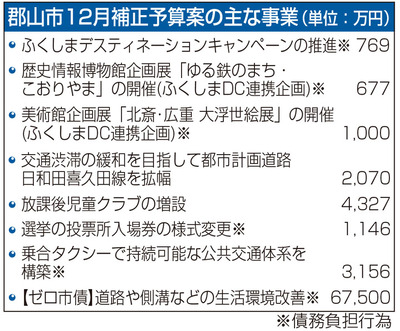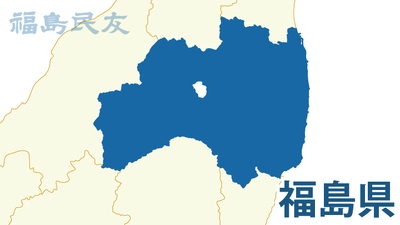実りの秋を迎えた会津盆地の西端、会津坂下町へ向かった。10年ほど前から文化財巡りに熱中している西沢書店(福島市)取締役の古川博さん(53)の案内で、地元でも知られていないような、隠れた仏像の魅力を探しに行った。
会津盆地は9世紀に法相宗の僧徳一らが仏教文化をもたらして以来、多くの寺院、仏像が創建され「仏都」と呼ばれる。「中でも戊辰戦争の戦火を逃れた、坂下など盆地の周縁には今も古い仏像が多く残っている」と古川さんは言う。
そこでまず向かったのは同町の北側、田園と山の境にある上宇内(かみうない)薬師堂だ。本堂へ入ると、邪鬼を踏みつける四天王の像を作り替えたとみられる5体の「十二神将」の像や3体の菩薩(ぼさつ)像。いずれも迫力満点だが、真打ちは奥の収蔵庫にあると、同所を管理する上宇内薬師会の斎藤満会長(78)に案内された。
コンクリート製の収蔵庫の鉄の扉を斎藤さんが開けると、重々しく黒光りした仏像が鎮座していた。国重要文化財の「薬師瑠璃光如来坐像」。像高183センチ。両脇に日光、月光2体の菩薩像を従える。戦前は国宝だった時期もあるという。斎藤さんは「湯川村にある国宝の薬師如来像よりも大きい」と誇らしげだ。
薬師像は、徳一が会津を訪れた頃より百数十年後の10世紀前半に作られたとされる。9世紀ごろの厳しい顔つきの仏像と比べ、柔和な表情が特徴。古川さんは「質量感がすごい」。
仏像は16、17世紀に頻発した水害と地震で数百メートル南にあった寺院が壊れ、野ざらしの時もあったという。元禄の頃に僧道安の手で現在の仏堂が建てられた。補修を繰り返した足回りは顔に比べて小さい。斎藤さんは「仏像の保存は代々受け継がれてきた。地域をまとめてくれる存在」と言う。
次に訪れたのは「立木観音」で知られる恵隆寺(えりゅうじ)。昼前から家族連れが多い。藤田恵盛(けいせい)住職(59)の案内で本堂へ入り、正面を覆う巨大な幕を引いてもらう。すると高さ8.5メートル、圧倒的なスケールの千手観音が目の前に現れた。
9世紀初頭の作という「立木千手観音菩薩立像(立木観音)」は、名前の通り立ったままの木を彫って作られたという。その左右にはそれぞれ約2メートル、28体の眷属(けんぞく)の像「二十八部衆」が広がる。まさに巨大なステージだ。
上宇内薬師と立木観音のあるこの地は、かつて近くを阿賀川と只見川が蛇行し、何度も水害に襲われたという。江戸時代初期には大地震にも見舞われた。疫病が流行したこともあったろう。そこで人々は仏像を守り続けてきたのだった。藤田住職は「多くの若い人に訪れてもらい、その歴史を知ってもらいたい」と話していた。
◇
上宇内薬師堂の拝観は事前予約が必要。1週間前を目安に電話で予約する。拝観料500円。立木観音は予約不要、拝観料300円。問い合わせは上宇内薬師会(電話0242・83・1953)、恵隆寺(電話0242・83・3171)へ。
歩いた後は本格コーヒー
見学後は、レストラン「ファットリアこもと」(電話0242・83・1101)で食事した。そばやイタリアンなどメニューが豊富で、バリスタの資格を持つ五十嵐玄さん(24)が入れる本格的なコーヒーも楽しめる。