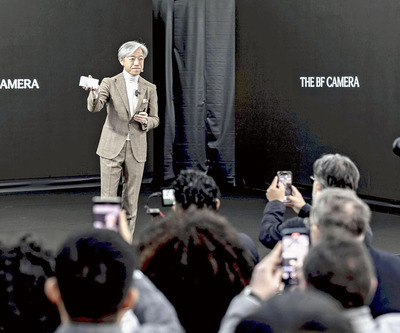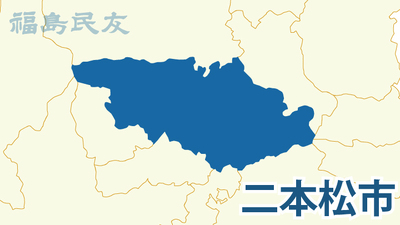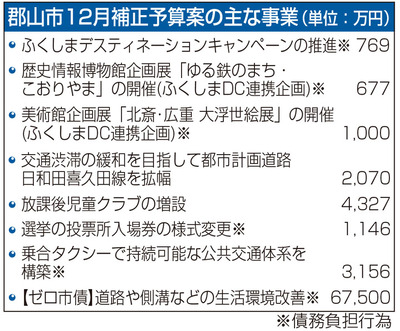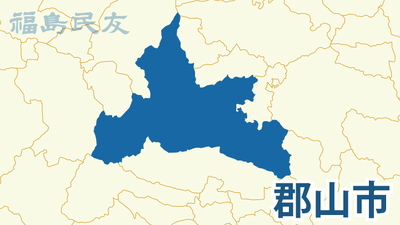東日本大震災と原発事故を契機に、避難所の生活環境は大きく見直されてきました。その中でも大きな課題となったのがトイレであり、その後の改善の動きは続いています。
国際的なスフィア基準では、避難所のトイレは20人に1基とされています。日本の「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」(内閣府、2024年改定)でも、発災直後は50人に1基、避難が長期化した場合は20人に1基を目安としています。さらに男女別や洋式化、多目的トイレの整備といった配慮も盛り込まれました。
実際に、熊本地震(16年)や能登半島地震(24年)では、仮設トイレの早期配備や洋式便器の導入、車いす利用者に対応できるトイレの整備が報告されています。また、断水時に下水道に直接流せるマンホールトイレや、自宅避難者向けに配布された携帯トイレの利用も確認されています。能登半島地震では、発災直後の避難所の約9割で携帯トイレが使われ、40日以上たっても一定の割合で継続利用されていたという調査結果があります。
一方で、十分な数を設置できない避難所や、清掃や汚物処理が追いつかず不便が生じるケースも報告されています。女性や高齢者、要配慮者に配慮した運営は地域差が大きく、依然として課題が残されています。
トイレは単なる衛生設備にとどまらず、健康や尊厳を守るために欠かせない存在です。改善の動きは着実に進んでいますが、現場で確実に機能させるためには、設備だけでなく、運営体制や人員の確保を含めた取り組みが求められています。