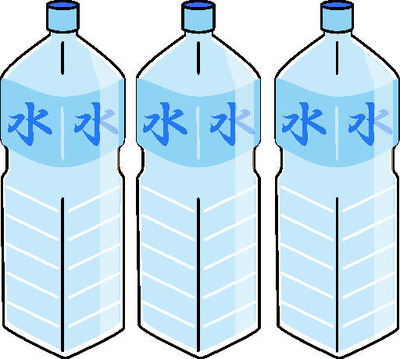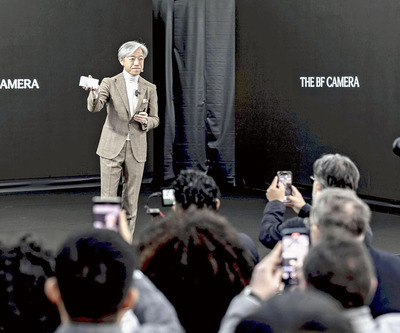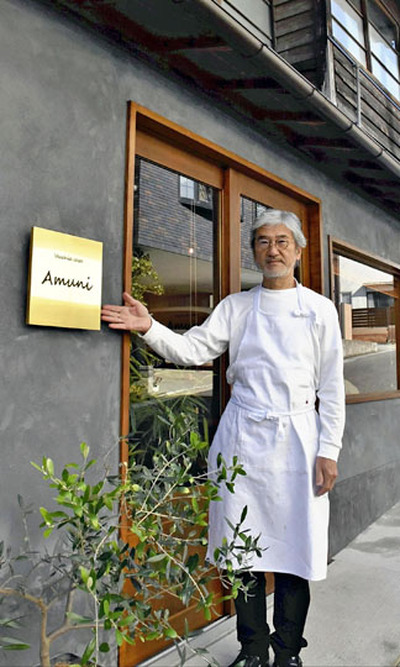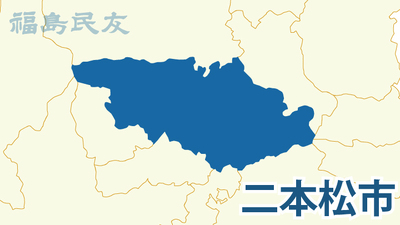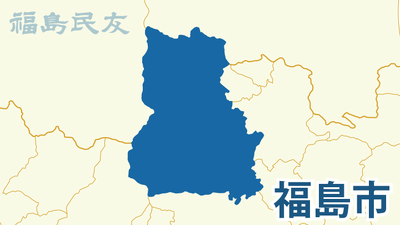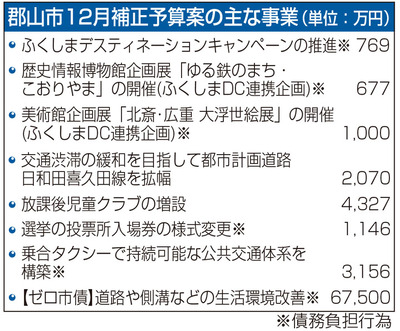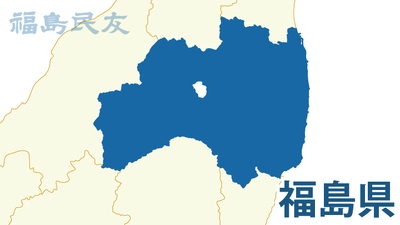東日本大震災と原発事故をきっかけに、避難所の在り方は大きく見直されました。その議論の中で注目されたのが、国際的な人道支援の指標である「スフィア基準」です。1990年代、アフリカ内戦やルワンダ難民危機などを受け、支援の質を確保するために97年に国際NGOが中心となって策定されました。 この基準は、被災者が人間らしい生活を守るための最低限を示すものです。例えば、1人あたりの居住空間3・5平方メー...
この記事は会員専用記事です
残り406文字(全文606文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。