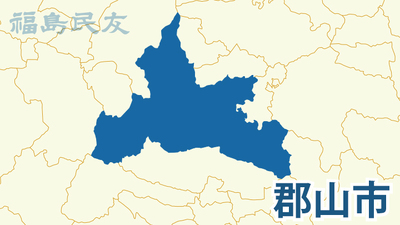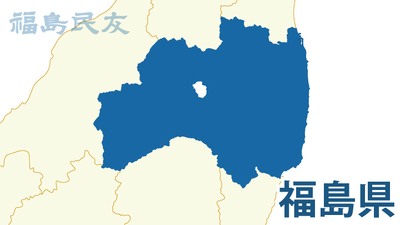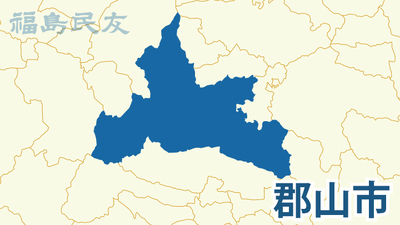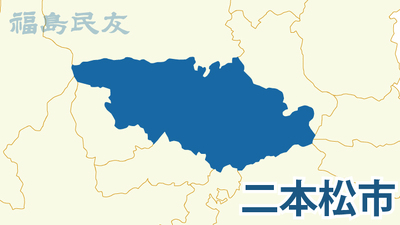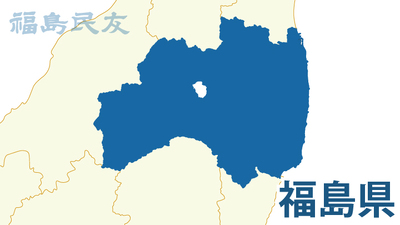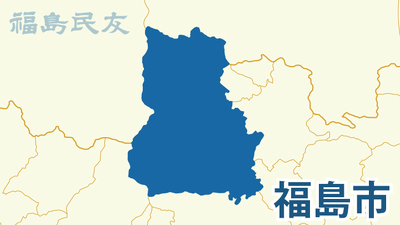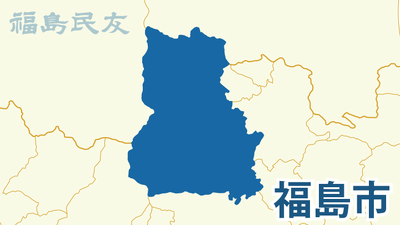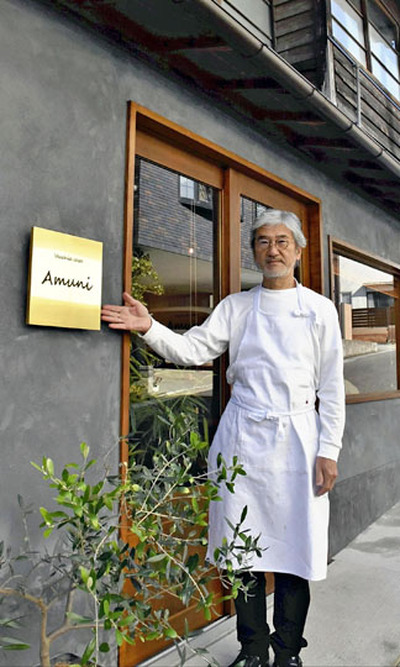調査目的:公益財団法人 交通遺児育英会(石橋健一会長)は、当会の全奨学生を対象に「ヤングケアラーの可能性」等の生活実態をより正確に把握し、今後の支援策検討に活かすために、昨年に引き続き2回目の調査を実施。
調査対象:当会の奨学生(743名の内467名が回答、回答率62.9%)
調査方法:Web調査、記入式調査併用
調査期間:2025年6月27日から7月25日
※本件調査実施、結果分析にあたり、外部専門家の監修をいただいております。なお、調査実施にあたり、事前に保護者に対して今回調査の趣旨等についてご理解をいただくためのお手紙をお送りしております。
■調査結果概要
・ヤングケアラーとして家族の世話をしている(含む過去)方は、奨学生全体で12.4%、うち高校生では全体の12.0%、大学・短大生以上で全体の12.8%と、全国調査と比較して当会奨学生のヤングケアラーの比率が高いことがわかります。主なお世話の対象者は父親か母親が多く、具体的なお世話の内容は「家事」(44.8%)、「外出の付き添い」(34.5%)、次いで「見守り」(31.0%)でした。
【参考】令和2年全国調査(三菱UFJ R&C):家族の世話をしている全日制高校生4.1%。(主な世話の対象者は「きょうだい」44.3%)。令和3年全国調査(日本総合研究所):家族の世話をしている大学3年生6.2%。
・お世話をしている高校生の50.0%、大学・短大生以上では42.1%が「ほぼ毎日世話」をしています。1日あたり3時間以上お世話に費やしている高校生が25.0%、大学・短大生以上では15.8%いることも明らかになりました。
・お世話の開始時期は、「7歳~12歳(小学生)から」が43.1%と多く、「6歳以下」との回答も5.2%ありました。お世話にしている期間については、「5~9年」が43.1%で最も多く、「10年以上」も15.5%おり、お世話が長期間に渡っている人が多いことが伺えます。
・ヤングケアラーの健康状態については、「精神的にきつい」との回答が高校生で10.0%、大学・短大生以上で23.7%、「時間的に余裕がない」との回答が高校生で10.0%、大学・短大生以上で18.4%ありました。
・相談の経験に関しては、高校生の50.0%、大学・短大生以上では63.2%が「相談したことがない」と回答しました。相談しない主な理由としては、「誰かに相談するほどの悩みではない」(高校生70.0%、大学・短大生以上66.7%)、「家族外の人に相談するような悩みではない」(高校生20.0%、大学・短大生以上20.8%)、「家族のことのため話しにくい」(高校生20.0%、大学・短大生以上4.2%)、「家族の状況をわかってもらえないと思うから」(高校生20.0%、大学・短大生以上4.2%)という回答でした。
・支援を求めていることとしては、高校生では「修学への特別支援金」(25.0%)、「家庭へのさらなる経済的支援」(20.0%)、「自由に使える時間が欲しい」(20.0%)、大学・短大生以上では「家庭へのさらなる経済的支援」(26.3%)、「進路や就職など将来の相談にのってほしい」(13.2%)が主な要望でした。
・お世話をしている奨学生のうち、自分がヤングケアラーに「あてはまる(含む過去)」との回答が36.2%で、「あてはまらない」との回答が27.6%でした。お世話をしながらもヤングケアラーであるという自覚をしていない方が一定数いることが伺えます。
・全奨学生のヤングケアラーの認知については「聞いたことがあり、内容も知っているが61.9%(前回調査60.1%)、「聞いたことはあるが具体的な内容はよく知らない」が19.1%(前回調査17.2%)となっており、前回調査時より認知率が上がっていることがわかります。
この調査結果については、当会ヤングケアラーの実態を深く理解する一助にするとともに(今後後も継続的に実施予定)当会の今後の支援プログラムの策定に活用して参ります。
当会では現在、ヤングケアラー対策検討プロジェクトを立ち上げて、ヤングケアラーと思われる奨学生への面談を進めており、早期に適切な支援を行うべく検討しています。