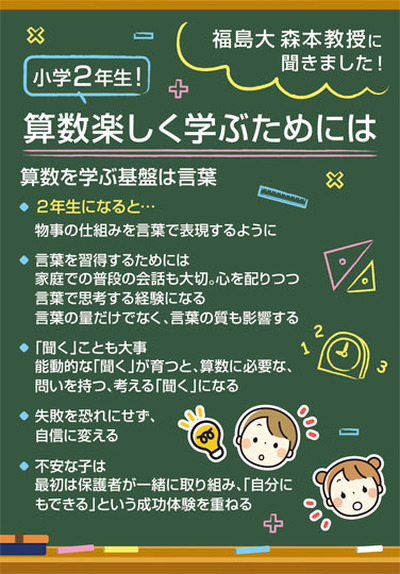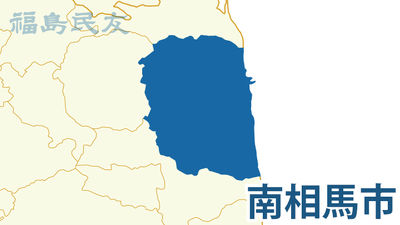子どもたちが未来に羽ばたくために、どんな教育が必要なの? ふるさとの未来はどうなっていくの? 子育て世代の関心が高いこれらのテーマについて、福島県の取り組みを内堀雅雄知事に聞きました。2回にわたり紹介します。今回は教育についてです。聞き手はふくしま子育て応援隊ナビゲーターで福島中央テレビアナウンサーの大橋聡子さんです。
■幼小連携進めて就学スムーズに
Q 幼稚園と小学校が連携する「幼小連携」が県内で進んでいます。狙いや効果を教えてください。
A 幼小連携の目的は子どもたちが小学校生活に円滑に適応できるよう支援し、幼稚園などで培った力を小学校でさらに伸ばせるようにしていくことです。特に「小一プロブレム」と呼ばれる、小学1年生が学校生活に慣れることができず困難を感じる状況を解消することが重要です。
幼稚園と小学校の子どもの交流活動を行ったり、授業に幼稚園などで行っていた活動を取り入れたりする取り組みが進んでいます。幼小連携の取り組みを進める市町村や幼児教育施設、小学校は増えてきています。今後、さらに多くの子どもたちが自分らしさを発揮しながら小学校生活をスタートできるように取り組んでいきたいです。
■中高一貫教育で生徒の力伸ばす
Q 来年度、県内3校目の公立中高一貫校ができます。中高一貫教育の狙いや効果について教えてください。
A これまで会津には会津学鳳中・高、浜通りにはふたば未来学園中・高を開設しました。来年4月には中通りの郡山市に安積高の併設中学として県立安積中が開校します。6年間にわたる計画的で継続的な教育課程と学習環境のもと、一貫した教育を行うことで、生徒の能力や適性を伸ばし、幅広い年齢集団の中で、さまざまな活動を通じて社会性や豊かな人間性を育むことを目指しています。
■福島に誇り持ち活躍してほしい
Q 中高一貫教育を通して、どのような子どもたちを育成したいですか。将来的に本県でどう活躍してほしいでしょうか。
A それぞれの中高一貫校の特色ある学びを通じ、子どもたちが夢の実現に向けて主体的に課題解決に取り組む力、グローバルな視点を持って社会を変革する力、未知の時代をたくましく開拓し新しい価値を創造する力を身に付けることを期待しています。そして福島に誇りを持ち、それぞれの分野のリーダーとして、地域や福島県、日本、世界で活躍することを願っています。
■海外研修を支援自由な発想期待
Q 県内の高校生が海外で活動する機会もあります。県のグローバル教育について狙いを教えてください。
A 県教委では、福島らしさを生かした多様性を力に変える教育に取り組んでいます。県の復興と地方創生を見据え、既存の枠組みや常識にとらわれず、自由な発想で新しいアイデアを生み出す教育を推進していく必要があります。このため、国際的な視点を持ちながら、さまざまな方々と連携して地域課題の探究活動に取り組むことで将来的に福島県の発展に貢献できる人材を育成することを目的に、本年度から県グローバル人材育成基金を創設しました。この基金は県内の高校生などの海外研修を支援するものです。
県は平成27年にイギリスのロンドンにある総合大学ユニバーシティー・カレッジ・ロンドン(UCL)と国際交流や人材育成、産業観光の振興などを目的に覚書を締結しました。本年度は夏に高校生3人を英国に派遣し、UCLやケンブリッジ大学の教授らによる特別講義やワークショップなどのプログラムを英語で体験し、文化交流も行いました。
■「タブレット使い学習の幅大きく広がった」
■情報を見極めてより良い学びに
Q 県内でもICT(情報通信技術)教育が進んでいます。知事の率直な感想は?
A 一番大きな変化は、子どもたちの机の上にタブレット型パソコンが置かれるようになったことだと思います。インターネットで分からないことを調べたり、写真や動画、プレゼンテーションソフトなどを活用して学びをまとめたり、共有したりすることができるようになったので、学習の幅が大きく広がりました。
各自がタブレットを持ち、学習状況に応じた練習問題に取り組めたり、家庭学習に活用できたりと、一人一人の興味や関心に合わせた学習がしやすくなったことも良い点だと思います。
遠く離れた場所や海外の学校との交流授業などが行われるようになり、学びの可能性もますます広がっていくことと思います。
一方で、インターネット上には虚偽の情報、誤った情報、フェイクニュースなどさまざまな情報が氾濫しています。このため、情報を正しく理解し、活用する力、リスクを判断して回避する力といった情報モラルを身に付け、メディアリテラシーを高めていくことで、子どもたちのより良い学びにつなげていくことも重要だと考えています。