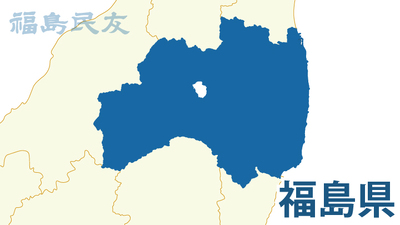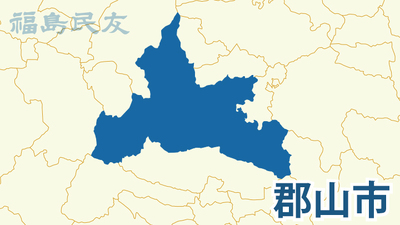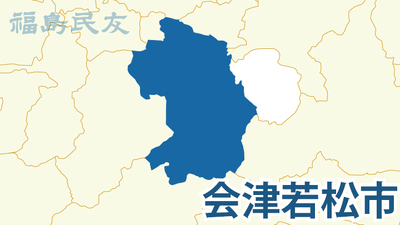阪神大震災の発生から、きょうで30年となる。節目の年に阪神大震災から得られた教訓や課題に理解を深め、現在進行形の災害支援や今後の減災へつなげていくことが重要だ。
阪神大震災は、近代都市が震度7の激震に初めて直面した災害で、神戸市を中心に6434人の犠牲者を出した。その多くが建物の倒壊や家具の転倒による圧死だったため、全国で建物の耐震化の対策が進むなど、国の対応が防災から減災へと大きくかじを切ったきっかけとされる。
住宅再建を国が公的に支援する「被災者生活再建支援法」の制定など、被災を巡る法制度が整備された側面もある。ただ、兵庫県立大の室崎益輝名誉教授は、これらの成果を評価しながらも、被災直後に設けられる避難所の環境などについては、神戸の経験が生かされず、能登半島地震でも課題として残されていると指摘する。
阪神大震災が発生した30年前より確実に高齢化が進み、劣悪な避難所の環境で住宅が再建されるまでの時間を過ごすことは、災害関連死に直結するより切実な問題になっている。国には、避難所の環境改善や仮設住宅の確保、速やかな生活再建の実現に向け、公的負担の増加も含めた法制度の抜本改正を図ることを求めたい。
阪神大震災が発生した1995年は、「ボランティア元年」と呼ばれた。被災地に多くの支援者が集まったことに加え、自主的に行動した住民らが行政の手が届かない被災者のニーズを捉え、支援やその後の地域再生に貢献したインパクトを表現した言葉だ。被災30年を経過した神戸では、復興計画に住民の意向が反映された地区の方が、持続的な地域再生につながっているとの指摘がある。
西日本の広い範囲では南海トラフ巨大地震、東北の太平洋側では日本海溝・千島海溝巨大地震の発生が懸念されている。いざという時に身を守る事前防災、発生時に災害弱者を取り残さない体制づくりなどには、住民の協力と主体的な参加が不可欠となる。県や市町村は、平時に地域の多様な主体が関わって合意形成できる環境づくりを進めておくことが大切だ。
神戸市では、阪神大震災時に生まれていなかった高校生らが地元の被災を見直し、教訓を学ぼうとする動きが出ている。東日本大震災と東京電力福島第1原発事故を経験した本県でも、震災を知らない世代が増えている。阪神大震災の節目に、家族や学校などで13年前の東日本大震災の体験を共有しておくことを心がけたい。