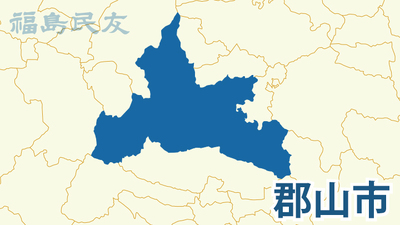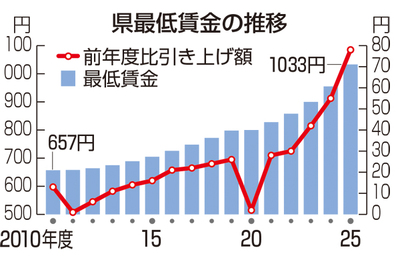環境省は5日、東京電力福島第1原発事故に伴う県内の除染で出た土壌の再生利用や県外最終処分への関心を高めようと、東京都内でパネル討論会を開いた。会場からは、課題となっている全国的な理解の醸成や共感を得るための取り組みに工夫が必要だとの指摘が相次いだ。
首都圏の住民ら約50人が参加した。県外最終処分への理解促進を目指す対話型の討論会は8月の福島市での開催に続いて2回目で、県外では初めて。参加者から質問や意見を募り、環境省幹部や放射線の専門家、地元住民の計3人が回答する形で行われた。
原発事故から14年半となる中、除染土壌の再生利用などに関する政府方針を知らない県外の人の割合は8割を超える。参加者の一人は、若い世代を含めて認知度が低い要因を質問した。
大熊町でキウイフルーツの生産に取り組む男性(大阪府出身)は「当事者意識がないことが根本的な原因だ」と指摘。積極的に関西の友人らを生産現場に招いているとし「農業や食を切り口に、まずは大熊町について興味を持ってもらい、その上で最終処分問題を含め福島の現状を伝えている」と周囲の関心を高めるための自身の取り組みを紹介した。
全国の自治体の首長を対象とした現地視察会の開催が再生利用の進展に有効との指摘も出た。環境省の中野哲哉参事官は「地方自治体の政策を決定する首長に中間貯蔵施設などを視察してもらう取り組みは大変意義がある」と応じ、視察機会の拡大に意欲を示した。
同省は6日も都内でパネル討論会を開く予定で、約100人の参加を見込んでいる。計3回の開催で得た教訓や知見を踏まえ、同省は「より効率的な理解醸成の取り組みの仕方を検討する」としている。