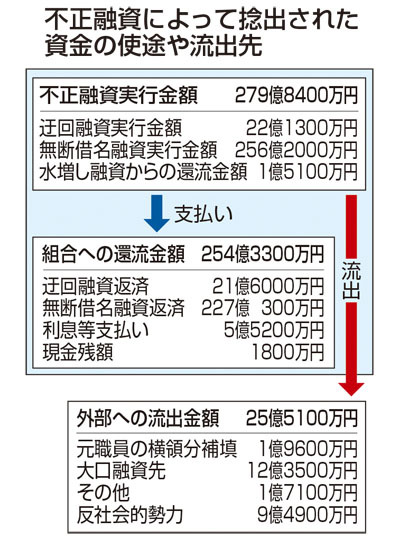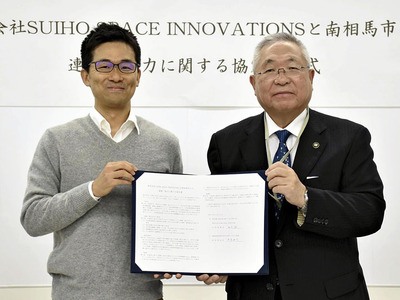生産と供給の安定化に資する指標を構築することが重要だ。
コメの単位面積当たりの出来具合を表す「作況指数」の廃止に向け、農林水産省が代替する新たな指標の概要を示した。直近5年間のうち、最も収量が多かった年と少なかった年を除く3年間の平均値で算出し、猛暑などの影響を反映させる方針だ。
作況指数の公表は1956年に始まった。過去30年間の傾向から水田10アール当たりの収量の平年値を割り出し、それを100として上回れば単位面積当たりの出来が良く、下回ると不作になる。良、やや良、平年並み、やや不良、不良の5段階で評価してきた。
2024年産の作況指数は101の平年並みで、農水省は生産量は足りていると説明していたが、実態との隔たりが指摘された。これまでの不作は、日照不足や低温などの冷害が主な要因だったが、近年は温暖化に伴う高温などの被害が大きいことが影響している。
約70年にわたる統計とはいえ、過去30年の傾向を踏まえた指標では、ここ数年の急激な気候変動に対応できないのは明白だ。指標は市場価格の動向とも密接に関わるだけに、精度を高めることが求められる。主食であるコメの安定供給のため、生産者や市場に信頼される指標に改めてもらいたい。
全国から水田約8千カ所を無作為に抽出して実測調査が行われている。調査員が現地で稲を刈り取り、玄米をふるいにかけて主食用米となり得る粒の量を単位面積当たりで把握し、これに全体の作付面積をかけて玄米の収量を見積もってきた。作況指数はこの単位面積当たりの収量を過去30年と比較して算出している。
こうした地道な作業にもかかわらず、収量と、実際に流通に回るコメの量で差が生じているのは高温障害で品質の落ちた粒が増え、玄米を精米した際に量が減りやすくなっていることがある。
また玄米をふるいにかけて選別する際の基準が農水省と農家で異なり、流通量が農水省の推計を下回る傾向にある。農水省が見積もった収量と、実際に流通するコメの量の差を縮めることが安定供給に欠かせない。農水省は出荷量を算出する基準などについても早急に検討する必要がある。
今回のコメ不足や価格高騰は、消費量の拡大に加え、ネット通販などの新たな販売方法での流通量が把握できていないことも要因とされる。生産量やそのために必要な作付面積の確保は、需要の把握が前提になる。農水省は需要見通しの精度を高めてほしい。