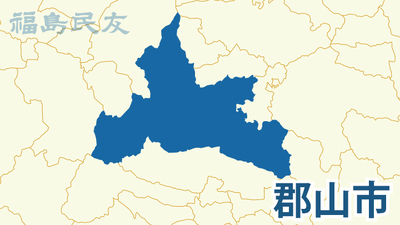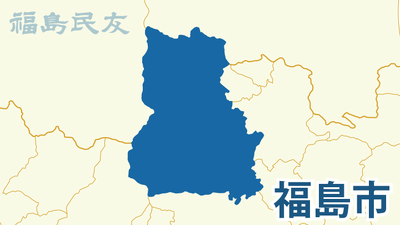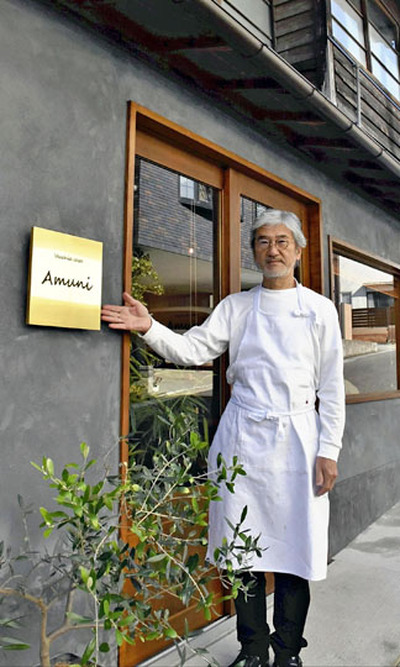公明党が自民党との連立政権からの離脱を表明した。両党は1999年に自由党を含めて連立政権をつくって以降、野党転落の時期も含め強固な関係を築き、政権奪取後も政権を支える土台となってきた。26年にわたる連立関係の解消は、国政の歴史的転換点だ。
公明は昨秋の衆院選、今夏の参院選の敗因となった「政治とカネ」問題の解消を巡り、自民から十分な回答がなかったことを理由とした。今後は「中道改革の軸」となることを目指すとしている。
自民は公明から企業・団体献金の受け皿の大幅な制限に踏み切ることなどを求められていたが、前向きな回答を避けた。その上、政治資金収支報告書に多額の不記載があった萩生田光一氏を党の幹事長代理に起用した。公明が自民の改革姿勢を疑うのは当然だ。
この問題に加え、公明と保守色の強い高市早苗氏では歴史認識や外国人との共生についても考えの隔たりが大きく、連立の継続は難しいと判断したとみられる。
一方の自民は総裁選の間もほかの野党との連立拡大を意識した発言が相次ぎ、高市氏を含め各候補とも公明への言及は少なかった。長年の関係から、公明が連立から離れることはないとの過信が自民側にあったのは疑いない。
公明は自民との選挙協力も白紙にする。自民は、小選挙区で公明の支持母体である創価学会の支援を得ることで議席数確保につなげてきたが、これも期待できなくなる。自民にとっては政権運営に加え、大敗が続いている選挙でも、大きな痛手となる。
公明は「平和の党」を旗印とし、安全保障などの面で「政権のブレーキ役」を自認していた。自民が単独で過半数を確保していた安倍政権以降は、集団的自衛権の行使などを巡り、自民に意向を押し切られる場面が増え、立ち位置が揺らいでいた。
公明は連立政権で、政策を巡る与党間の協議や国土交通相などのポストを通じ、自党の政策実現を図ってきた経緯がある。連立解消により今後は自民の意向に左右されることはなくなるが、政策を実現する力が低下することは避けられない。多党化が進むなかで、党の独自性の発揮と政策実現をどう図っていくのかが問われる。
連立解消で、高市氏の首相指名は不透明さが強まった。物価高対策など国政課題が山積し、月内には日米首脳会談が行われる見通しだ。政治空白がこれ以上続くことは許されない。新たな政権の枠組みづくりに向け、与野党には責任ある対応が求められる。