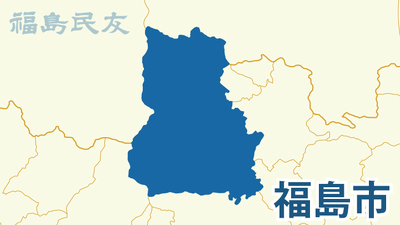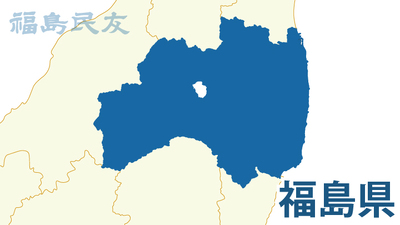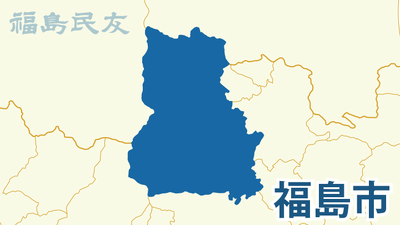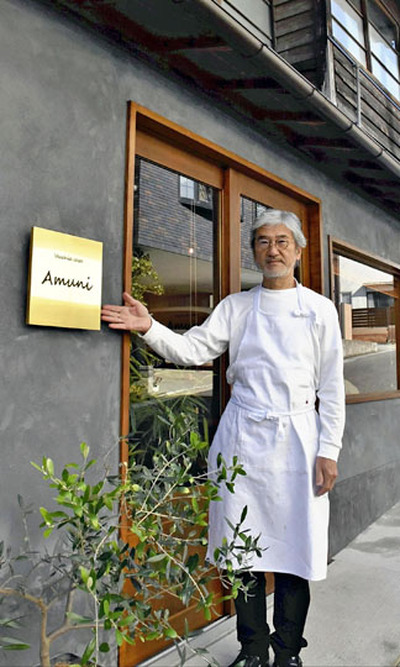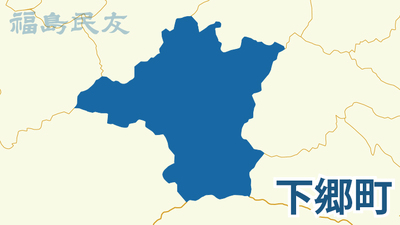場当たり的な施策を繰り返し、歳出を膨らませるのは、財政や将来への不安を広げるだけだ。政権が目指す「強い経済」を実現するための対策には成り得ない。
政府は21兆3000億円規模の経済対策を決定した。財源の裏付けとなる2025年度補正予算案の歳出は17兆7000億円規模で、24年度の補正予算より4兆円近く拡大した。新型コロナウイルス禍後では最大規模だ。ガソリン税の暫定税率廃止、「年収の壁」引き上げによる減税効果も見込んだ。
最優先となる物価高対策では、電気・ガス料金の一般家庭の負担を7000円ほど軽減する補助金や、子ども1人当たり2万円の給付などが盛り込まれた。自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」を拡充し、1人当たり3000円程度のおこめ券や電子クーポンを配れるようにする。
自民党が参院選公約に掲げ、野党から「ばらまき」と批判された一律2万円の現金給付は見送られたが、いずれも家計を救うための一過性の支援策に過ぎない。おこめ券では、高止まりした米価の値下がりを遅らせる恐れさえある。経済の好循環を生み出し、物価高を克服できるかは疑わしい。
経済対策は、危機管理投資や成長投資、防衛力と外交力の強化も柱に据えた。造船や人工知能(AI)、先端半導体などの分野で官民連携投資などを促すため7兆2000億円を盛り込んだ。こうした成長戦略は、停滞が続く日本経済の起爆剤として期待できる。
しかし補正予算は本来、災害や経済危機などの緊急対応で編成される。首相が「責任ある積極財政」を掲げているとはいえ、危機管理や成長、防衛などの費用はじっくり議論を積み重ね、本予算に計上すべきだろう。これでは「規模ありき」との批判は免れない。政府は国会審議を通し、施策の効果や必要性などを説明すべきだ。
財源は税収の上振れ分や特別会計の9000億円を活用するものの、多くを国債の発行で賄う。首相は当初予算と補正予算を合わせた25年度の国債発行額は、24年度の42兆1000億円を下回る見込みだと説明し、「財政の持続可能性にも十分配慮した」と強調した。
一方、金融市場では、国債の増発で財政が悪化するとの懸念から長期金利が上昇し、為替は円安傾向が続いている。金利上昇は国債の利払い費の増加、円安は輸入品価格の上昇を招き、物価高につながるだけだ。これでは経済対策の意義を問われかねない。首相は財政再建への道筋も語り、市場や国民の懸念を払拭する必要がある。