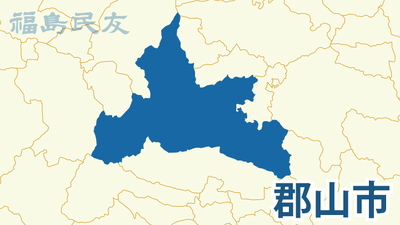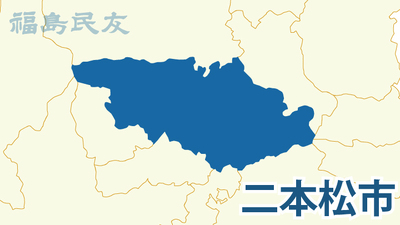新潟県の花角英世知事が、東京電力柏崎刈羽原発の再稼働を容認する考えを表明した。再稼働が実現すれば、2011年の東日本大震災で福島第1原発事故を引き起こした東電の原発で、初の事例となる。国と東電は知事の判断に対し、最大限に安全性を確保することで応えなければならない。
柏崎刈羽原発は、新潟県柏崎市と刈羽村にまたがる原発で、7基が全て停止している。東電は13年、原子力規制委員会に6、7号機の再稼働審査を申請し、17年に合格していた。再稼働には地元の同意が必要で、花角氏の判断が注目されていた。花角氏は、国に安全対策の向上などの7項目の対応を求め、再稼働容認を明言した。
新潟県の県民意識調査では、再稼働の賛否は容認が50%、反対が47%と拮抗(きっこう)し、「再稼働の条件は整っているか」との問いには、否定的な回答が60%に及ぶ。県民にすれば、発電した電気は首都圏で使われるにもかかわらずリスクは地元で背負うのかとの思いもあるだろう。国と東電は、事故防止策の強化や丁寧な説明を続け、理解醸成を図らなければならない。
東電を巡っては、21年に柏崎刈羽原発でのテロ対策の不備が相次ぎ、規制委から事実上の運転禁止命令が出た経緯がある。命令は23年に解除されたが、県民意識調査で「東電が原発を運転することは心配」と答えた人が69%に上るなど、強い不信感を持たれている。
東電は、原発1基が稼働すれば年間1千億円の収支改善が図れることから、再稼働を渇望してきた。花角氏の判断の前には、再稼働を条件に1千億円を地域活性化のため拠出する考えを示した。しかし、東電が優先すべきは利益や内部の論理ではない。不祥事やミスを隠すことなく、誠実に新潟県民に向き合うことが重要だ。
国が認定した住民避難計画によれば、事故時に避難や屋内退避が求められる半径30キロ圏内には、9市町村の約41万6千人が居住している。県内を中心に広域避難先を決めているが、自然災害と重複し避難先が被災した場合には、県外への避難も視野に入れている。
本県の原発事故では、長期避難などで2千人超の震災関連死が生じた。花角氏は福島第1原発の視察などを通じて、事故の可能性は決してゼロにならないと実感したはずだ。新潟県は、事故の惨状を知った上で再稼働を容認したのであれば、誰一人命を落とさない避難体制を構築する責任がある。
原発事故が起きれば、影響は県境を超える。国と東電は隣県の不安解消にも取り組む必要がある。