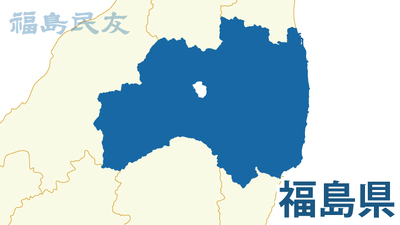暴言や過度なクレーム、不当な要求、交流サイト(SNS)での誹謗(ひぼう)中傷など、その行為は過激になっている。労働者が安心して働ける職場づくりが急務だ。
顧客や取引先が理不尽な要求をするカスタマーハラスメント(カスハラ)から労働者を守るため、国内すべての企業、自治体に対策を義務付ける関連法が来年10月1日に施行される見通しになった。今年6月に改正労働施策総合推進法などが成立し、法律の公布後1年半以内に施行するとしていた。
カスハラそのものを規制するのではなく、被害の発生を抑止する方策や、発生した場合の被害回復策といった対応を義務付ける。厚生労働省は暴行や脅迫、侮辱などの具体的な事例を明記し、警察への通報など対応方法を盛り込んだ指針案を示した。
カスハラ対策の強化は従業員の労働環境の改善に直結し、人材確保にもつながる。企業、自治体は指針を踏まえ、効果的な対策を講じてもらいたい。
指針ではカスハラの具体例として、契約金額の著しい減額要求、無断撮影、SNSへの投稿をほのめかして脅す―などの行為を挙げている。加害者には顧客や取引先だけでなく、介護施設などの利用者や家族もなり得るとしている。
対応方法では、可能な限り一人で対応させず、労働者は管理監督者に直ちに報告して指示を仰ぐことなどを示した。加害者に対する警告文の発出、出入り禁止の措置も有効な手段とした。
民間の調査によると、企業でクレーム対応を行った経験のある人のうち、顧客からカスハラや不当な要求を受けた経験があるのは7割を超え、その割合は高まる傾向にある。心身の不調などを訴え、休職や離職を余儀なくされる例が後を絶たず、人手不足に悩む企業にとっても影響は大きい。
これまで日本企業が重視してきた「顧客第一主義」は、サービスの向上などに貢献してきたが、カスハラを生む土壌にもなっていた点は否めない。たとえお得意さまであっても行き過ぎた行為を見過ごさず、毅然(きぜん)と対応しなければならない。企業や労働者の意識改革を進める必要がある。
一方で、顧客のまっとうな主張や意見を受け入れず、現場だけで漫然とカスハラと判断してしまうことなどがあれば、企業などにとって大きなマイナスになる。
それぞれの職場環境に応じ、どういう行為がカスハラに該当するかなど、職場の規定やマニュアルなどに具体的に判断材料を示しておくことが重要だ。