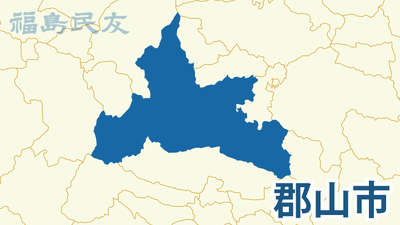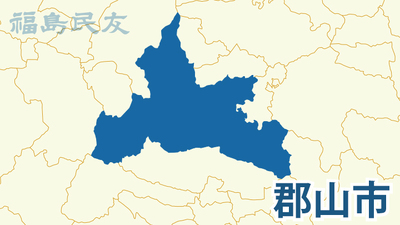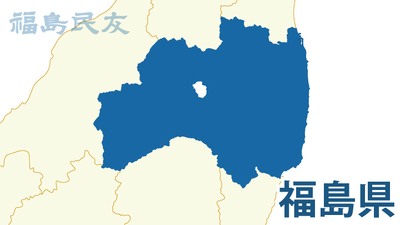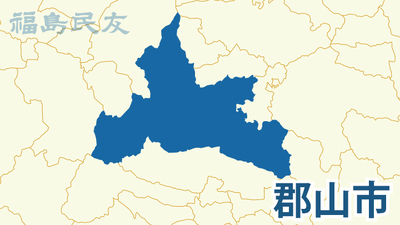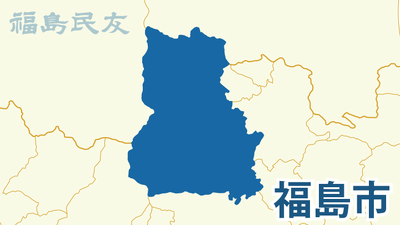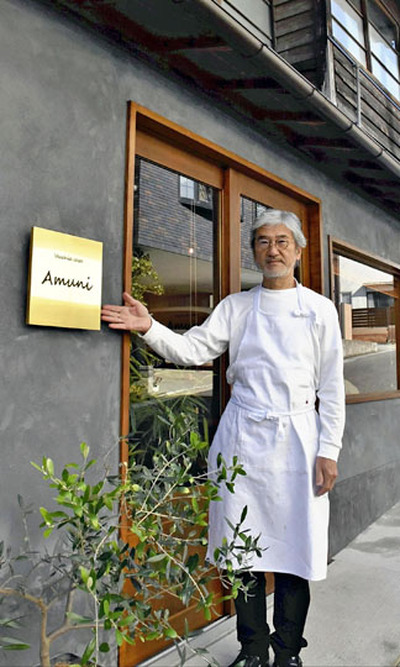県は本年度、複数の集落にまたがり、地域の維持や活性化に取り組む農村型地域運営組織(農村RMO)の育成を強化する。中山間地などの農村地域の住民が、人口減少が進む中でも安心して生活することができる環境づくりにつなげていくことが重要だ。
農村RMOは、農家だけではなく自治会や社会福祉協議会などのさまざまな団体で構成する。小学校の学区に相当する範囲で、農地の保全や地域資源の活用、高齢者の買い物支援や見守りなどの生活支援に取り組むことが期待されている。農林水産省は、実証的な取り組みやデジタル機器の導入を補助する制度を設け組織化を支援しているが、県内ではわずか5団体の設立にとどまっている。
県は、集落の枠を超えて農家や団体が連携するノウハウの不足が壁になっているとみている。そのため、合意形成の方法などをまとめた県独自の手引書を策定する。総戸数が9戸以下になると、集落活動の実施率が急激に低下するというデータがあり、その前の段階での対策が必要とされている。県は説明会の開催などを通じ、自立した地域運営に意欲がある農村RMOの結成を促してもらいたい。
農村RMOは、農地の保全団体が自治会など他の団体と連携することで組織する場合もあれば、地域の営農組織が直売所運営や買い物支援などに活動を発展させるケースもある。いずれの事例でも、地域内の限られた人材だけで幅広い取り組みを企画、運営していくのは難しいことが想定される。
県や市町村はこれまでの地域振興策を実施する中で、社会貢献に関心がある企業や団体、NPO法人らとの関係がある。行政には部局の垣根を越え、必要とされる知識を持った人材の紹介や課題解決に役立つ補助制度の導入などを支援する体制を整え、RMOの取り組みを後押ししてほしい。
農水省は、農村RMOが人口減少を踏まえた地域の土地利用を主導することも見込んでいる。これまで通りに維持することが難しい農地については、シソやエゴマなど手間がかからない作物の植栽や、体験型農園としての利活用、鳥獣被害を防ぐ緩衝地帯への転換などが選択肢となる。
体験型農園としての利活用は、家庭菜園に興味がある都市部の住民らが地域に関わる機会を生み出す。シソやエゴマの栽培や加工の委託は、新規就農や移住の受け皿にもなり得る。農村RMOの結成を、住民が地域の将来を考え、関係人口の増加などに取り組む契機とすることも求められる。