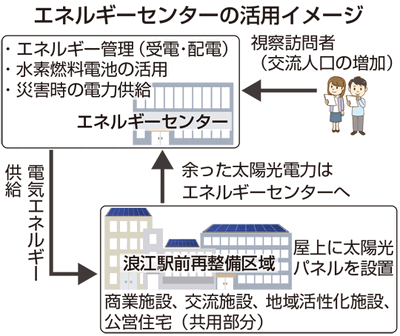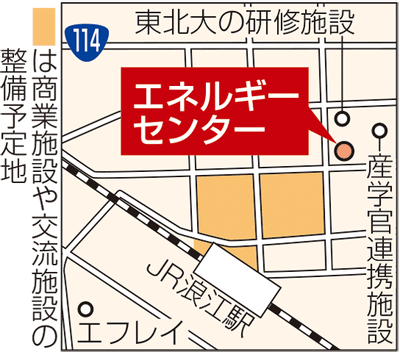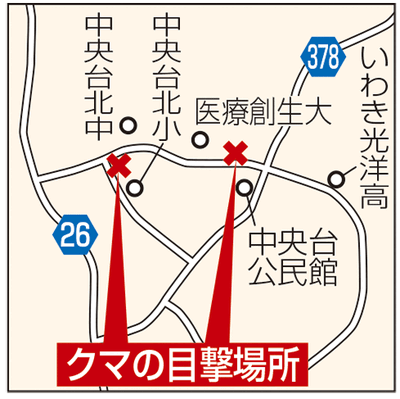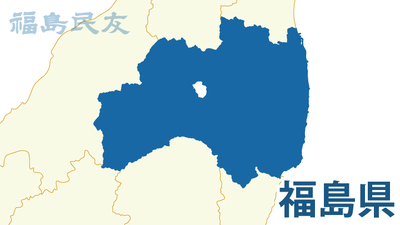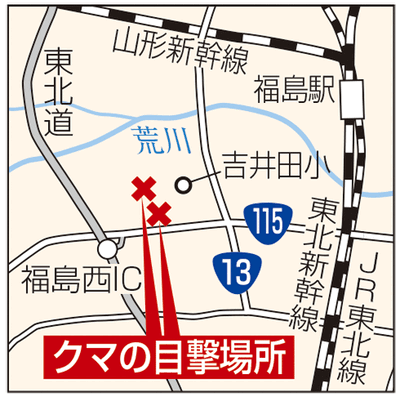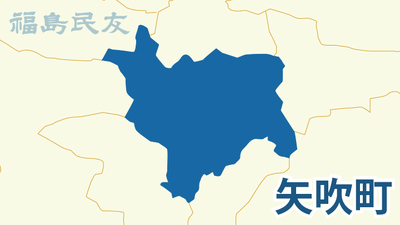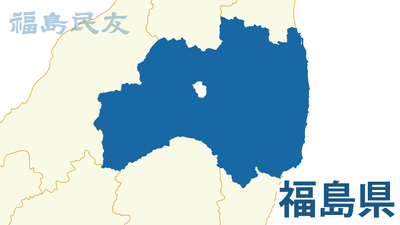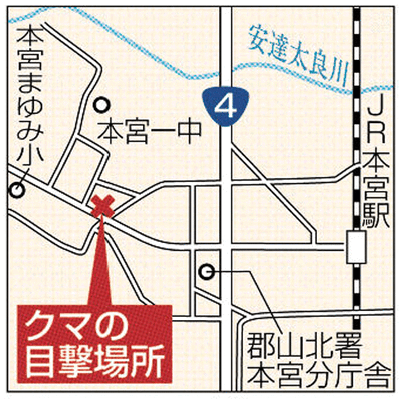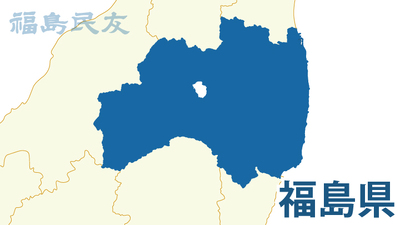浪江町はJR浪江駅周辺に商業施設や交流施設を整備する開発事業に伴い、再生可能エネルギーで発電した電気を最大限に施設で活用するための拠点「エネルギーセンター」を整備する。センターから駅前の各施設をつなぐ送電線網を整え、太陽光や水素エネルギー由来の電気を供給する仕組みをつくり、脱炭素社会の実現と水素の利活用促進に向けた、先進的なまちづくりのモデル構築を目指す。
町が13日、浪江駅前の旧浪江小跡地に整備する産学官連携施設の住民説明会で、センターの整備計画を示した。2027年度中の着工、整備完了を目指している。町は駅周辺に整備する商業施設や交流施設、公営住宅の屋上に太陽光パネルを設置。発電した余剰電力をセンターが管理し、高圧受電設備「キュービクル」を通して、地域活性化施設を含めた駅前の各公共施設の需要に応じて電力を供給する。
センターには水素燃料電池や水素トレーラーの貯蔵庫も整備。町内に立地する福島水素エネルギー研究フィールドと連携する方針で、同フィールドで生産された水素を燃料電池に供給し、水素から発電した電気も駅前の各施設で活用する考え。将来的には発電する際に発生する熱の有効利用も視野に入れる。センターへの視察を受け入れ、交流人口の拡大につなげる。
センターは、産学官連携施設と東北大の研修施設の隣接地に建設される予定。町は当初、駅周辺整備事業に関する基本計画で、水素燃料電池などを施設ごとに分散配置する計画だった。しかし、効率的な電力供給を実現させるために拠点を設けて集約することにした。駅前周辺の施設整備を巡っては、公営住宅が27年12月、交流施設や商業施設、地域活性化施設は28年3月の完成予定となっている。