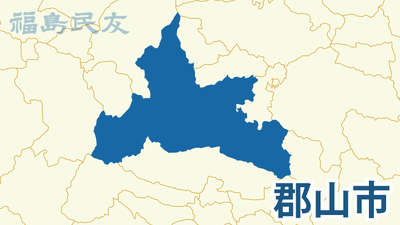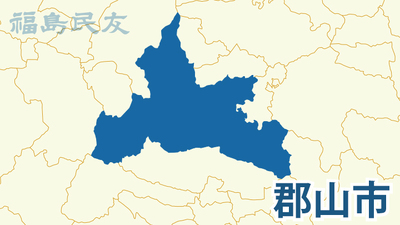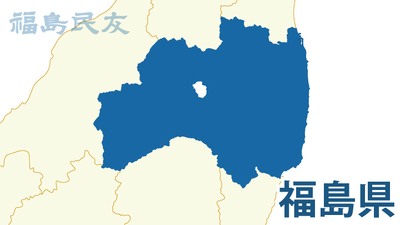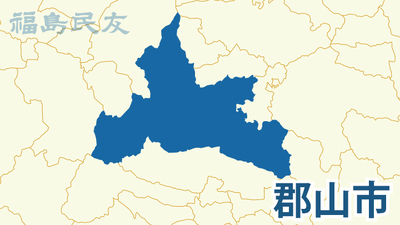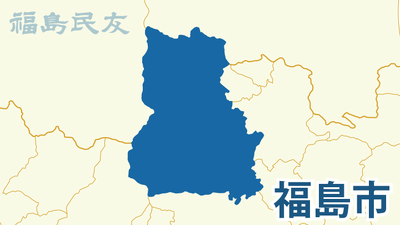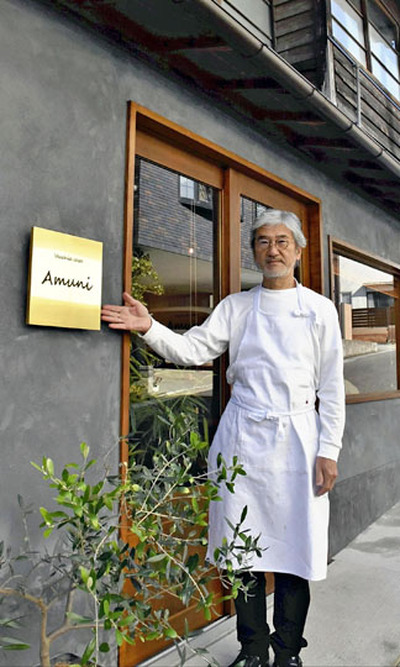「ネット社会/それでも頼る/この一面」を代表標語とする新聞週間が始まった。真偽の分からない多種多様な情報があふれている現代だからこそ、正確な情報が掲載されている新聞を、自らが社会と向き合うための羅針盤として活用してもらいたい。
私たちの生活がインターネットと切り離せなくなって久しい。交流サイト(SNS)の浸透や、生成人工知能(AI)の発達で、新聞やテレビなどのマスメディアでなくとも、多くの人に向け情報を発信できるようになり、世論や選挙結果に影響を及ぼすようになっている。こうしたインターネットの影響力の拡大は、新聞が果たすべき役割にも変化を与えている。
今夏の参院選では、本紙を含めた各紙が政党や候補者の訴えや、選挙に合わせてSNSなどで発信されている情報の真偽の検証を行った。「外国人は日本人よりも簡単に生活保護を受給できる」「期日前投票は書き換えられたりすり替えられたりする」といった誤った情報については、明確に誤りであると指摘したのは、その代表的なものだ。
選挙に限らず、不正確であったり偏ったりした情報に基づく判断は、社会が誤った方向に進むことにつながりかねず、極めて危うい。流布している情報の真偽の確認を積極的に行うことなどを通じて、ニュースに対する理解を助ける役割を強めていきたい。
新聞の大きな特徴の一つが、多種多様な記事が掲載されていることだ。自分が関心を持っている記事だけでなく、世の中のさまざまな動きを知るきっかけになる。当初は興味のなかったテーマの記事を読んで、今まで考えもしなかったものの見方や社会の動きを知ることができる。
ネットにも幅広い事柄に関する情報が掲載されているものの、それまでの閲覧履歴などから、見る人が興味を持っていそうなものが表示されやすいようになっている。例えば不動産の情報を検索すると、それに関した広告表示が増えるのは、多くの人が経験しているだろう。ニュースやSNSの記事の表示にも同じような仕組みが用いられている。
自分の興味関心に沿った情報が得やすいのは確かに便利だが、それ以外の情報が届きにくくなるという弊害もある。
自らが生きる社会がどのようなものであるかを把握するには、一つの面からのみ眺めるのでは十分とは言えないだろう。社会を立体的に捉えるための道具として新聞を役立ててほしい。