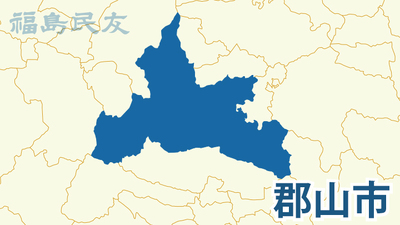白血病などの治療のために血を造る幹細胞の移植が必要な患者のうち、実際に移植を受けられるのは、その半数にとどまる。患者と同じ型の幹細胞を持つ提供者が見つからないためだ。今月は、骨髄バンクの推進月間だ。誰かの命を救うため、自分にできることを考えるきっかけとしたい。
幹細胞提供者(ドナー)の登録を担う日本骨髄バンクによると、登録者は56万人おり、移植が必要な患者は県内の26人を含む1760人いる。移植は年約千件行われているが、患者とドナー登録者の幹細胞の型が適合する割合は極めて低く、適合する相手がなかなか見つからない患者もいる。
患者に適合する幹細胞が見つかる可能性を高めるには、ドナー登録を増やすことが不可欠だが、全国的に減少している。本県では約1万4千人が登録しているものの、この5年で千人以上減っている。ドナー登録できるのは18歳から54歳までで、55歳になると登録から外れる。ドナー登録が多いのは団塊ジュニアの世代を含む50代のため、新たな登録者が増えなければ減少がいっそう加速する。
幹細胞を提供してもよいという人は、県赤十字の血液センターや県の保健福祉事務所などに相談してほしい。
県骨髄バンク推進連絡協議会と県は高校生を対象に骨髄バンクをテーマとした映画を上映したり、献血などの場で説明する機会を設けたりしている。こうした活動を広げ、若い世代の登録につなげることが重要だ。
連絡協の運営委員長の青砥安彦さんは「骨髄という言葉から脊髄や背骨をイメージして、幹細胞の採取が危険なのではと敬遠する人もいる」と話す。また、幹細胞の型が一致した場合は必ず提供しなければならないと考え、登録をためらう人も多いという。
幹細胞は脊髄ではなく、腰や腕の骨から採取する。ドナーや家族が提供を断ることもできる。依頼があってから提供するかを決められることも知っておきたい。
移植の際、ドナーは仕事を休むなどして数日間入院する必要があるが、そのための特別休暇を認めている企業は少ない。県は、ドナーの入院などの費用を支援している市町村に対し、その半額を助成する制度を設けているものの、21市町村は支援制度がない。
型が適合した人が移植に協力したくとも、仕事や費用の理由で断念するのは避けねばならない。行政や企業は移植の際に休みを取りやすい環境を整えることで、ドナーを支援してほしい。