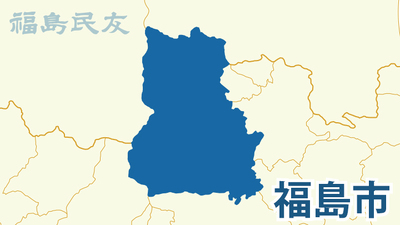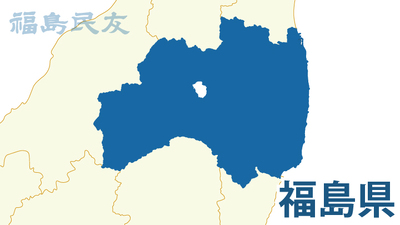JR只見線が、2022年10月の全線再開通から3年を迎えた。新潟・福島豪雨の甚大な被害から復活した同線は、住民の交通手段としての役割に加え、「地方創生路線」となることが期待されている。県や沿線の自治体が奥会津の重要インフラとして利活用を進め、交流人口の拡大などにつなげていくことが重要だ。
只見線は、会津若松駅から新潟県魚沼市の小出駅を結ぶ約135キロの路線だ。11年7月の豪雨では、鉄橋流失などで会津川口―只見駅間が不通となった。県やJRの協議の結果、不通から復旧する区間の管理を県が担う「上下分離方式」を導入し、公費を含む約90億円をかけ全線を再開通させた。
全線再開通後は、県管理区間の1日1キロ当たりの利用者数を100人とすることを目指し、受け入れ態勢の整備などを進めてきた。23年度は103人で目標を達成したが、24年度は69人に落ち込んだ。県は「再開通による注目度が薄れたことが原因」と分析する。
只見線は絶景が多く、鉄道ファンからの評価は高い。奥会津の文化を学ぶ「学習列車」に昨年度36校の1504人が参加するなど、新たな利活用も出ている。県は、只見線をより魅力ある観光資源に成長させていく決意を新たにし、効果的な広報と幅広いニーズの掘り起こしを続け、底堅い利用者の確保につなげなければならない。
只見線には、台湾から多くの観光客が訪れている。現地では旅行経験者が口コミなどで魅力を伝えるなどの好循環ができている。ただ、実際に訪れるのは、人気の第1只見川橋梁(きょうりょう)(三島町)の周辺に集中しているのが現状だ。移動手段は、バスと列車を組み合わせた事例が多い。国内のツアーも同様の傾向にあるという。
只見線で観光列車を企画するとほぼ満席になるなど、路線の集客力は高い。第1只見川橋梁以外の名所の周知や観光列車の増便、マイカー客が一部乗車する「ちょい乗り」ができる環境の整備を進めれば、人の流れは広がり、経済波及効果も大きくなる。県や沿線自治体がJRと連携し、独自の観光列車の配備や利便性が高い運行ダイヤへの改正も視野に入れた幅広い対策を講じていく必要がある。
県が管理を担う会津川口―只見駅間では、電気や土木の工事、路線の保守作業を自前で行わなければならない。現在はJRなどからの応援を得ながら、人員を確保している。安全で安心な只見線の運行を継続するため、県には鉄路の維持を担う専門的な人材の確保や育成も十分心がけてもらいたい。