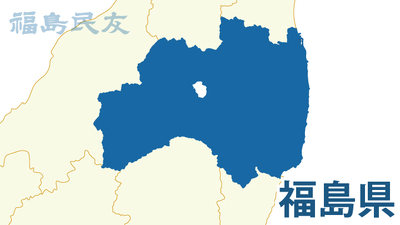本県沿岸漁業の2024年の生産額は、東日本大震災前の10年の約4割に当たる36億1千万円だった。国や県は、漁業者や流通業者、加工業者など水産業に関わる各段階での支援を強化し、生産額の上乗せを図る必要がある。
本県の沿岸漁業の生産額は、2020年から4年連続で増加し、23年には震災後で最高の39億6600万円を達成した。24年は総水揚げ量は前年と変わらなかったものの、シラスやヒラメなどの魚種の水揚げが落ちたことが原因となり、前年比で3億4千万円の減少となった。
県は農林水産業振興計画で、30年に生産額を100億円とすることを目標にしている。震災後に一時休漁したことなどで、本県沖の水産資源は豊かになっている。漁業者には、魚の数や大きさが確保されている環境を壊さないようバランスを取りながら、計画的に出漁数を増やすことで生産額を着実に引き上げてもらいたい。
震災前は、宮城、茨城両県沖に出漁する「入会(いりあい)操業」が行われ、生産額を底上げしていた。震災による中断を経て、宮城県沖では23年から本県漁業者による沖合底引き網漁船による操業が再開されたが、茨城県沖ではまだ実現していない。漁業団体は、隣県の団体と丁寧な協議を続けてほしい。
24年度に沿岸漁業に新規就業した人は27人で、調査を開始した09年度以降で最多だった。このうち、将来的に主力となる39歳以下の若年層は、全体の6割強の18人に上る。震災前5年間の新規就業の平均が約10人だったことに比べると、人材確保は漁業再生に向けた好材料となっている。
県は現在、海洋環境と漁獲の情報をタブレット端末を使ってリアルタイムで確認し、効率的に新鮮な魚を取れることを可能にするシステムの導入を進めている。若手漁業者らと連携しシステムのさらなる普及を図るなどして、高品質の水産物を安定して供給できる体制を整えることも大切だ。
本県漁業を巡っては、東京電力福島第1原発事故やその後の処理水放出による風評が懸念されていた。しかし、24年の東京都消費地市場での県産水産物の平均単価は、震災前年と比較して2割増で、流通量を増やせば売れる状況となっている。
ただ、仲買人や卸などの流通業者の力が、震災前より縮小しているとの指摘がある。県には、販路開拓など現場に密着した指導をしている福島相双復興官民合同チームと歩調を合わせ、手厚く支援していくことが求められる。