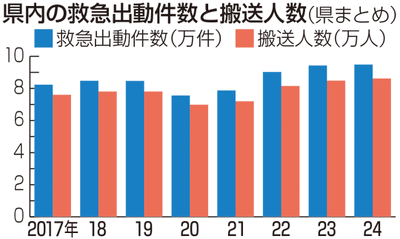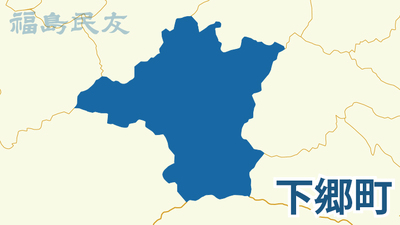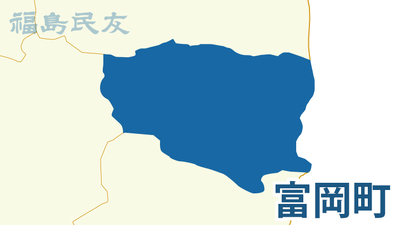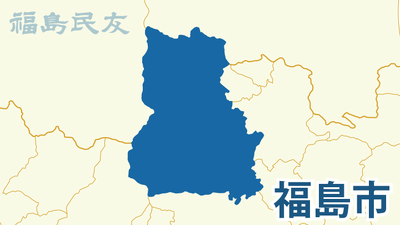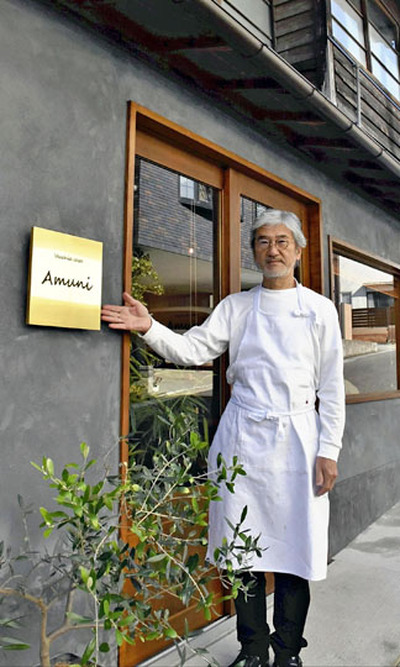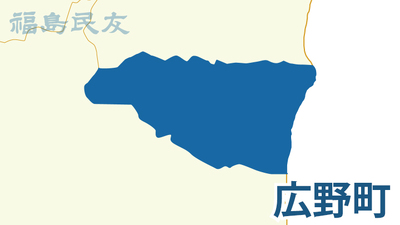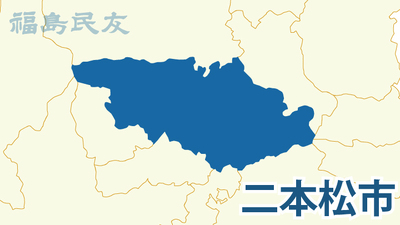福島県で運用開始から3年目を迎えた救急電話相談「#7119」の利用が広まっている。救急車を呼ぶかどうか迷ったときの相談窓口で、県によると2023年度は1万5916件、24年度は2万3367件の相談があり、本年度も4~10月で1万4121件と前年度を上回るペースで相談が寄せられている。高齢化などによる救急搬送件数の増加は社会問題化しており、救急現場の切迫を抑える効果が期待される。一方、高齢者の利用が少ないなど周知に関する課題も浮き彫りになっている。
「♯7119」は、急な病気やけがをして救急車を呼ぶべきか、すぐに診察を受けるべきかなどを迷ったときに、看護師らに電話で助言を受けられる仕組み。
総務省消防庁によると、先進導入地域では救急搬送者のうち軽症者割合の減少や不急の救急出動の抑制、119番通報をためらっていた潜在的な重症者の発見など、救急車の適切な利用につながっている。
高齢化の進展や熱中症の増加などで新型コロナウイルス禍の時期を除いて増加傾向にあり、昨年は約9万5000件、約8万6000人となった。
消防庁の統計によると、全国で昨年搬送された人のうち、入院を必要としない軽症だった人の割合は46.8%だった。県は軽症者の割合を公表していないが、本県も全国と同様の傾向にあるという。
県によると「#7119」に昨年度寄せられた相談の中で、緊急性が高いとして119番通報するよう助言したのは1801件、緊急性が低いとして医療機関の受診を勧めたのは9379件だった。応急処置の方法を尋ねる相談もあった。
ただ、県政世論調査で「#7119」を知っていると回答した人は26.2%にとどまる。利用者は20~30代が多く、年齢が上がるにつれて少なくなる傾向にあり、救急搬送される割合が高い高齢者への周知が課題だ。県は「救急現場の圧迫を抑える要因になっている。救える命を救うために利用してほしい」(地域医療課)と促している。
福島市消防本部によると、昨年の救急搬送は1万4110人で、このうち4割以上の6811人が軽症だった。救急車をタクシー代わりに使うような明らかに不適切な利用は減少しているが、担当者は救急出動件数の増加を肌で感じていると明かし「迷ったら『#7119』に電話をかけてほしい」と呼びかける。