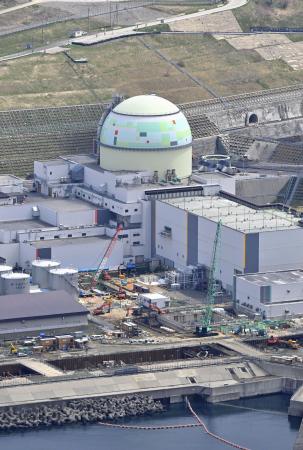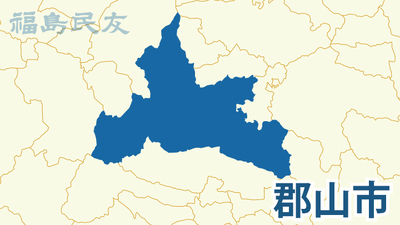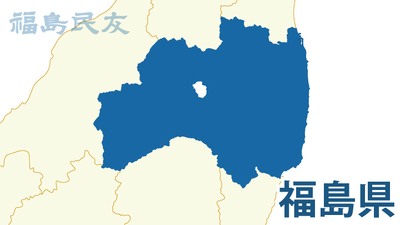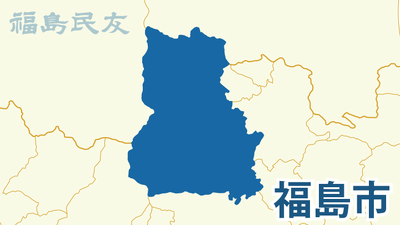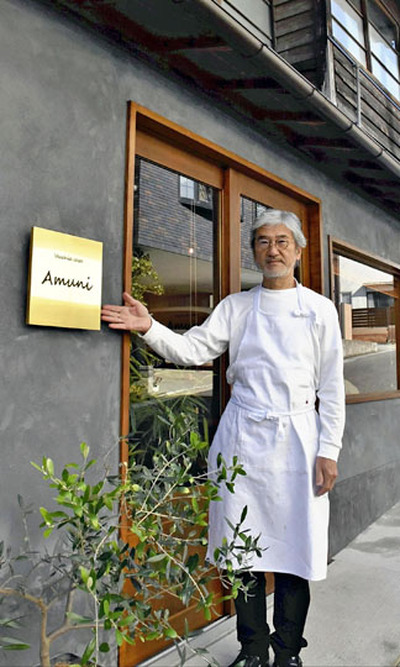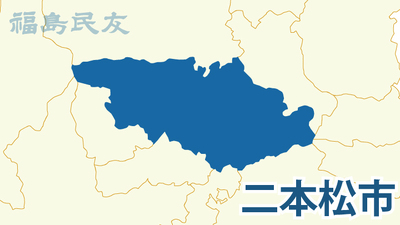大阪大特任教授の坂口志文さん(74)は過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」を発見、その成果はさまざまな病気の治療へとつながった。偉業を成し遂げるまでには不遇な時代も経験したが、ひた向きに努力を積み重ね、世界中の研究者が追究する一大テーマの基礎を築いた。
免疫学の魅力に触れたのは京都大医学部時代。体内への外敵の侵入を防ぐ免疫機能が自分の体を傷つけるという「自己免疫疾患」の存在を知った。
京大大学院に進んだものの、免疫について深く学ぼうと中退。1977年に移った愛知県がんセンターで、免疫機能に関わる胸腺を取り除いたマウスは自己免疫疾患になるという研究に接した。
日米の大学や研究所で「免疫を抑える免疫機能」の研究に取り組んだ。当時、提唱されていたリンパ球の一種「サプレッサーT細胞」は存在しないことが分かり、研究は徐々に下火に。自身が発見した制御性T細胞は同一視され、論文を出しても評価されない時代が続いた。
95年、制御性T細胞の目印となる分子を特定。2003年には細胞に関わる重要な遺伝子の特定に成功した。