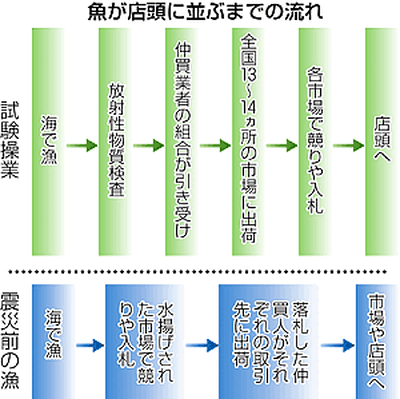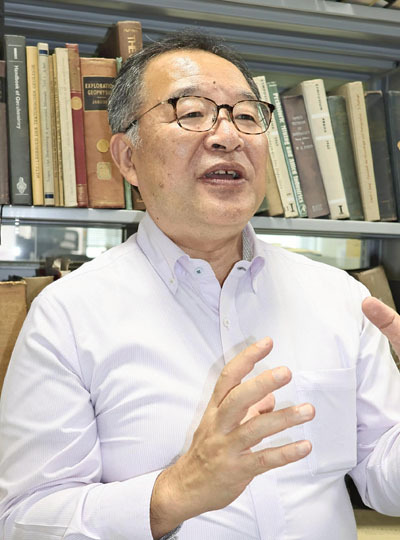東日本大震災と東京電力福島第1原発事故以降、本県沖で行われている試験操業は、8月で開始から約4年2カ月が経過する。対象魚種は開始当初の3種から、73種(4月現在)に増加、着実に本格操業への歩みを進めている。 試験操業は、国の出荷停止指示が出されている魚種を除く、本県沖の魚を対象に実施されている。魚種を限定し、小規模な操業と販売を試験的に実施し、出荷先での評価を調査しているほか、流通させることで...
この記事は会員専用記事です
残り968文字(全文1,168文字)
続きを読むには「みんゆうプラス」の会員登録もしくは
「福島民友新聞購読」の申し込みが必要です。