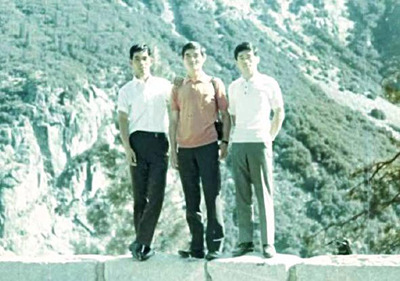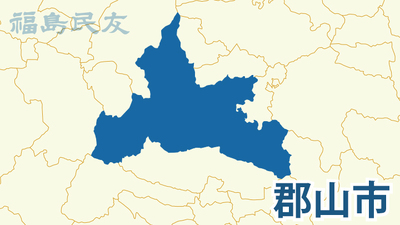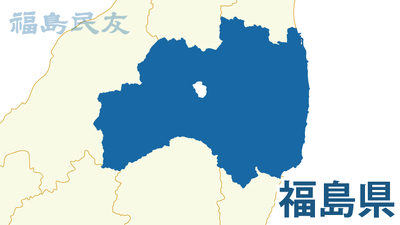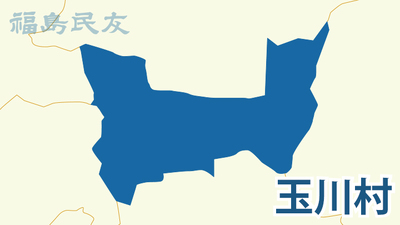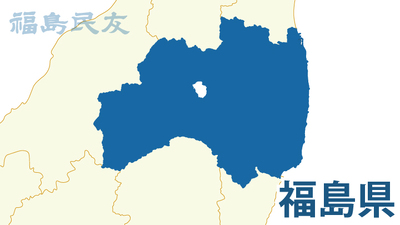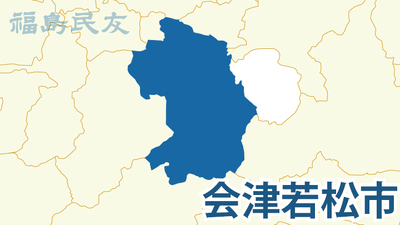米国研修が転機になった。
酪農は、乳牛3頭と1・5ヘクタールの草地を引き継いで始まった。その後、十数年で経営の規模は成牛40頭、育成牛20頭、草地面積14ヘクタール、トラクター3台まで拡大することになる。
規模拡大のきっかけは、県が初めて実施した農業経営者海外派遣事業だった。父の勧めもあり、私はすぐに手を挙げ、米国で農業を学ぶ機会を手にした。
村から研修に参加したのは、私を含め3人だった。当時、村内では「そんな超大型の経営を学んで一体何の役に立つのか」との声もあった。しかし、振り返ると勉強になることばかりだった。
研修は約2週間。米カリフォルニア州の数軒の農家を訪問した。まず驚かされたのが、米国の農業経営はどれも大型で、必ず経営者がいる点だった。さらには技術者やメキシコからの労働者を雇っていた。
では、当時の村の農業はどうか。米国の「経営者」「技術者」「労働者」に当たる仕事を一人で担うか、家族で行っている状況だった。さらには、誰よりも暗いうちから働きに出て、誰よりも遅くまで働くことが理想とされていた時代だ。これでは経営はままならず、もはや古い考えだと感じた。経営感覚の重要性を学んだ私は、資金繰りや情報収集も含め、経営者としての能力に力点を置いた酪農経営をしていくことを誓ったのだった。
もう一つ、気付かされたことがある。それは、視察したどの農家も立派な事務所を持っていることだった。事務所内には家族の写真や飾り物が置かれていた。仕事と生活はしっかり区別しながら、経営と生活の両面を大切にし充実させていたのだ。それは、数年後に研修で訪れた欧州でも感じたことだった。
忙しい中でも生活が充実するよう、働き方をどうデザインするか。農業や酪農の具体的な技術はもちろん、人生において重要となる新しい考え方を学べたことは、大きな収穫だった。