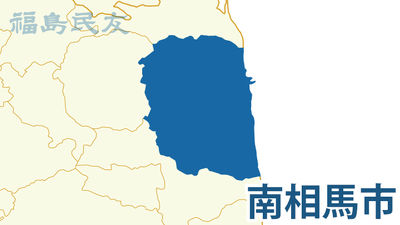心理的な傷を負ったり、財産を失ったりした犯罪被害者が、スムーズに必要な支援を受けられるようにすることが重要だ。
県などは、犯罪被害に関する相談や支援をワンストップで行う新たな枠組みをつくる。ふくしま被害者支援センターや県、市町村などが個別に行っている被害者の相談対応を一本化する。
被害者に対する支援は医療費や生活費といった金銭的なものから、心理面のケアなど多岐にわたる。これまでも捜査機関が被害者に相談窓口を紹介していたが、それぞれの分野を担う機関に被害者側からアプローチせねばならず、同じ説明を繰り返さなければならないなどの心理的な負担が生じることに加え、適切な支援を受けられないケースもあった。
新たな枠組みでは、県や市町村、支援センターのほか、弁護士会などのうち、どこか一カ所に相談すれば、各機関が提供する支援を受けられるようになる。県が新たに配置する「犯罪被害者等支援コーディネーター」が各機関との調整役を担う。警察が本人の了承を得た上でコーディネーターに被害者の情報を伝えることができるようにもする。
本県では、コーディネーターを支援センターに関わる臨床心理士が務める。各機関はコーディネーターとの連携を密にすることで、被害者により適切な支援を提供してもらいたい。
多くの関係機関が連携することにより注意しなければならないのは、被害者のプライバシーをどう守るかだ。見舞金の支給や生活費の支援などは被害者の居住する市町村が担うが、役所などに知人が勤務していたり、加害者の関係者がいることを恐れたりすることで、相談をためらってしまうケースがあるという。
被害者が支援を求めたことにより、被害の内容を多くの人に知られてしまうなどの二次被害を受けることは避けなければならない。情報共有の際には、それを知り得る担当者を狭く設定するなどの配慮を徹底し、被害者にもそういった取り組みを説明するなどして、支援を受ける上での不安を解消していくことが求められる。
県内59市町村のうち41市町村は犯罪被害者支援に関する条例を制定し、50市町村が見舞金などの制度を設けているものの、まだ地域差があるのが現状だ。被害者の住んでいる市町村によって、受けられる支援に差が生じることは望ましくない。枠組みの構築が、こうした格差の解消などにつながることも期待したい。