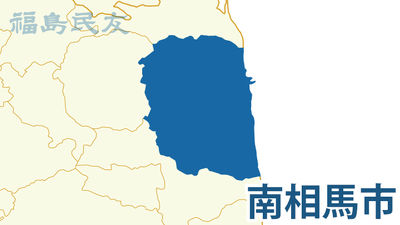東京電力福島第1原発で発生する処理水の海洋放出開始から2年となった。これまで計13回の放出量は10万トンを超えた。懸念された周辺海域での放射性物質濃度の基準値超えなど、目立ったトラブルはなく、放出が続いている。
処理水の放出は、第1原発構内に設置された保管タンクを減らし、燃料デブリの取り出しを安全に行うためのスペースの確保や、タンクの老朽化などによる予期せぬ漏水を防ぐことにつながる。廃炉作業の加速に欠かせない。
放出がトラブルなく続くことは本県などの水産物の輸入規制の撤廃を働きかけていく前提となる。トラブルがあれば、水揚げを急速に回復させている漁業への影響も懸念される。
東電と政府は国際原子力機関(IAEA)の監視などで客観性を担保しつつ、計画に基づいて安定した放出を続けることで、安全性に対する信頼を積み上げていくことが大切だ。
放出したのは保管している処理水の5%だ。現在も128万トンが保管されている。10万トン超を放出しているものの、保管量の減少は6万トンにとどまっている。汚染水の発生が続いているためだ。
原子炉建屋にある燃料デブリの冷却に用いた水に、建屋に流れ込んだ地下水や雨水が混じることで1日当たり約80トンの汚染水となる。そのうち7割超を地下水などが占める。地下水の流入対策として設けられた凍土遮水壁などが導入された後も、外部から建屋内に入る水の遮断は十分とはいえず、建屋の配管が集中する箇所の止水措置などを続けている。
早稲田大の松岡俊二教授(環境経済・政策学)は「放出が長引けば、機器の保守点検や、(放射性物質の除去で生じる)汚泥処理などに伴う問題が起きやすくなる。汚染水の発生抑制に取り組まないと、海洋放出はいつまでも続く」と指摘する。東電はデブリの取り出しに向けた作業と並行する形で、汚染水が生じる要因となっている地下水や雨水の流入対策を強化する必要がある。
放出開始に伴い、東電は保管タンクの解体に着手しているが、現在保管中のものも腐食などが確認されるなど老朽化が進んでいる。処理水が今後も増える一方で、タンクの解体を進めていく必要があることも踏まえれば、処理水の7割を占める、放射性物質の除去が十分ではない水の再浄化を進め、放出可能な容量を増やしていくのは急務だ。現在の年5万トン超の放出量を拡大するなど、保管量を減らすことも検討すべきだろう。