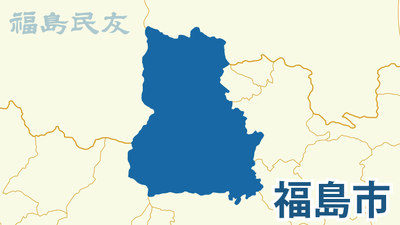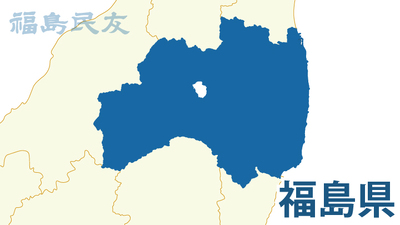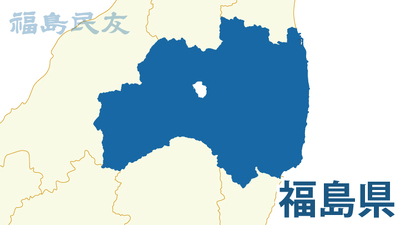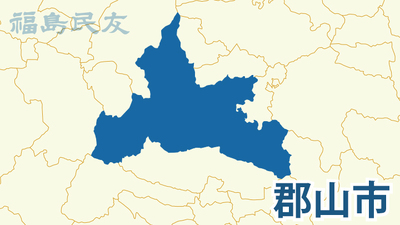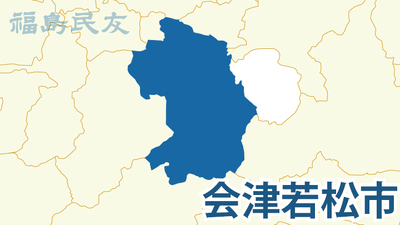使用時間の目安を法令で定めることに賛否はあっても、過度な依存が心身の健康などに及ぼす影響は無視できない。家庭で適切な利用について考える契機にしたい。
愛知県豊明市議会が、仕事や勉強時以外の自由時間でスマートフォンやゲーム機などの使用を1日2時間以内を目安とするよう住民に促す条例を可決した。小学生以下の使用は午後9時まで、中学生以上18歳未満は午後10時までとすることも求めた。罰則はない。全住民を対象に使用時間の目安を示した条例は全国初という。
条例はスマホなどを生活必需品と認めたうえで、睡眠時間の減少や家族の会話が短くなるなど、健康面や生活面への影響を指摘している。市は「2時間は一律のルールではなく目安」としており、施行後に睡眠時間の変化や家庭内のルール作りについて定期的に住民アンケートを実施する方針だ。
スマホは生活を便利にしてくれる一方、視力の低下や生活リズムの乱れ、精神面の影響などが懸念されている。特に子どものネットやゲームへの依存は、学力低下のほか、いじめなどのトラブルの原因にもなりかねない。
市民からは「個人の権利を制限するのか」との批判、市議会では「使用時間の目安に根拠はあるのか」などの質問もあった。条例はスマホとの向き合い方を模索する現代社会に一石を投じた形だ。今後、条例の効用、住民や地域への影響を注視する必要がある。
条例が家庭での自主的な取り組みに焦点を置いたのは注目すべき点だ。総務省の調査では、平日より休日にスマホなどのモバイル機器を利用する時間が増え、特に10~20代はその傾向が強い。学校や仕事から帰宅後、SNS(交流サイト)の利用や動画の視聴に時間を費やす人も多いとみられる。
条例が促す家庭内のルール作りは、過度な使用を回避するために有効といえよう。まずは家族全員でそれぞれの使用時間を確認し、どのように削減に取り組むかを考えることが鍵になる。本県でも実効性のある取り組みを共有し、実践していく必要がある。
オーストラリアでは昨年12月、16歳未満のSNS利用を禁止する法律が成立し、写真や動画共有アプリなどの利用も禁じた。事業者には年齢確認を義務付け、違反には制裁金を科している。
情報を入手し、取捨選択できる権利は尊重されなければならず、一律的な規制は望ましくない。ただ事業者については、利用者の過度な依存や犯罪などに誘導しないよう国は監視を強化すべきだ。