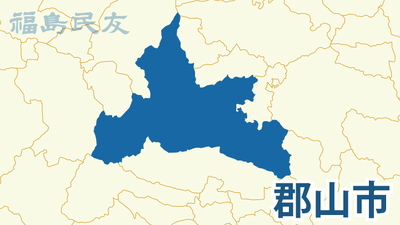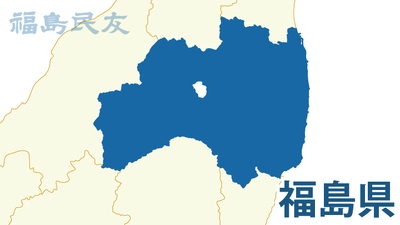2024年度の県内の再生可能エネルギーの導入量が、エネルギ
ー需要の約6割に達し、過去最高を更新した。県は、40年度にエネルギー需要の100%を再エネで生み出す目標を掲げる。さらなる導入には、環境と調和した在り方を模索していく必要がある。
本県は震災後、「再生可能エネルギー先駆けの地」として再エネ導入を進めてきた。浜通りや阿武隈山地での復興の観点を重視した発電所整備が導入の主軸となってきたが、固定価格買い取り制度(FIT)を背景に売電収入を見越した民間投資も行われてきた。ただ、その中の一部は、工事や立地などを巡り地元と軋轢(あつれき)を生じている。
県は現在、地産地消型の発電を目指す事業者の支援制度の準備を進めている。対象は、発電する電力の7割以上を県内の企業などに供給する事業者を想定している。売電収入の3%以上を立地自治体の活性化に役立てることも条件とする予定だ。地元との協議が前提のため、開発ありきの施設整備に歯止めをかける効果も期待される。県は制度の利活用を通じ、地域社会と協調した再エネ導入を主流にしていくことが求められる。
24年度に導入された再エネは大規模水力を除くと4535メガワットで、震災直後の11年度と比べると約12倍に増えている。導入量を大幅に伸ばしてきた主な要因は、各地で進む太陽光発電施設の整備だ。休耕地などを活用したメガソ
ーラー整備に加え、住宅用の機器導入が進んだことも相まって、19年度から6年連続で新規再エネ導入量の約8割を占めている。
太陽光発電を巡っては、自然環境の保全と開発のバランスの問題が顕在化している。メガソーラーの候補地となる場所も限られる中、大規模開発を中心とするのは持続可能ではない。県は、家庭や企業での中小規模の施設整備、壁面などに使うことができる「ペロブスカイト太陽電池」の利活用に軸足を移していくことが重要だ。
太陽光に頼らない形を構築するためには、風力や小水力、地熱、バイオマスなどの発電を伸ばしていくことが欠かせない。県は、事業として成立する可能性がある候補地や気象条件の調査結果などを広く事業者らと共有し、関連施設の整備を促してもらいたい。
県内のエネルギー需要を再エネで賄う目標の達成には、40年度の需要量そのものを減らしていくのも手法の一つだ。県や自治体、民間企業などが歩調を合わせて省エネや蓄電に関する技術を積極的に導入していくことで、環境に優しい社会を実現してほしい。