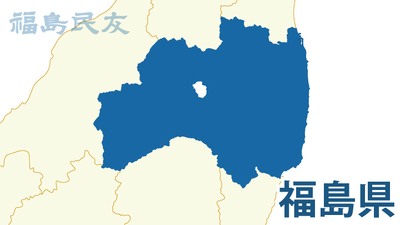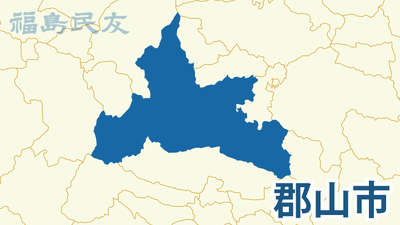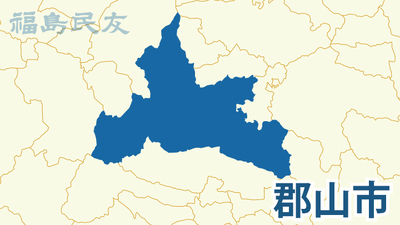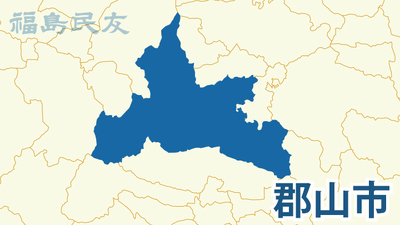党利党略ではなく、民意を的確に反映させるための政権の枠組みを目指す必要がある。
公明党の連立政権からの離脱を受け、21日に見込まれる首相指名選挙を巡る与野党の動きが佳境に入っている。立憲民主党と国民民主党、日本維新の会の野党3党はきのう、党首会談を行った。立民は、国民民主の玉木雄一郎代表を野党統一候補とすることを視野に3党連携を呼びかけた。
自民党の高市早苗総裁もきのう野党各党の党首や代表と会談し、国会運営や政策実現への協力を求めた。比較第1党の自民、最大野党の立民を中心に、衆院での過半数確保に向け、多数派工作が繰り広げられているが、その行方を左右するのは衆院で35議席を有する維新や、国民民主の動向だ。
国民民主の玉木代表は「政権を共にするのであれば基本政策の一致が不可欠だ」と強調し、憲法や安全保障、エネルギー政策などの基本政策の一致を連携の条件に掲げる。自民とはおおむね一致している一方、立民とは安全保障や原発政策で隔たりが大きい。
連立を組む政党間で国家観や基本政策が異なれば、政権運営は常に危険をはらむ。民主党政権下の2010年、沖縄県の米軍普天間飛行場の移設問題を巡り、社民党が連立から離脱し、政権は3年余りで終わった。こうした経緯も踏まえ政策を重視するのは当然だ。
ただ各党がそれぞれの主張を譲らず、相手に譲歩を求めるだけでは前に進まない。大同小異の状況にあるならば、互いに一致点を見いだすために努力を尽くすのが、責任政党としての使命だろう。
国民民主は自民との協議で、ガソリン税の暫定税率廃止、所得税が発生する「年収の壁」の引き上げの年内実現を求めている。自民、公明、国民民主の3党は昨年12月に暫定税率の廃止で合意していたが、自民は先の通常国会で廃止法案の採決を拒否した。公党間での約束をほごにした格好だ。
公明の連立離脱も政治改革を巡る不誠実な対応が引き金となった。自民は政権を維持し、史上初の女性首相誕生を目指すならば、誠実に他党と向き合い、政策をすり合わせ、実現を目指すべきだ。
新たに連立政権を発足すれば、具体的な政策などの協議にとどまらず、政党間の選挙区調整などの難題にも向き合わなければならない。短絡的に数合わせで政権をつくっても、早晩行き詰まることは過去の歴史が示している。
多党化が進む中、政党間の連携なしに政治は進まない現実を、各党は強く自覚してもらいたい。