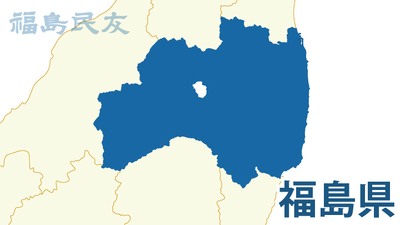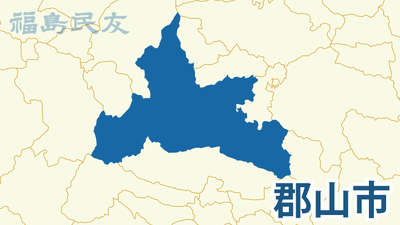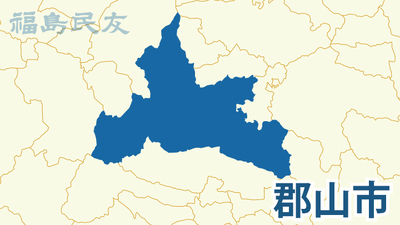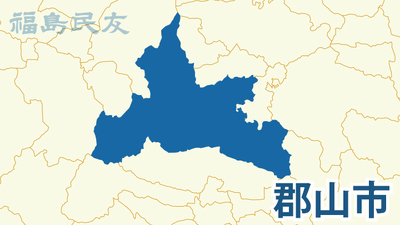県は年度内に、災害発生時の避難所運営マニュアルを改定する。7月に太平洋側に津波警報が出された際、自治体の避難所の備えなどに課題があったことを受けた対応だ。次の災害時に「想定外」の事態に陥らないよう、改定を避難所のハード、ソフト両面での改善につなげていくことが重要だ。
7月の津波警報は、ロシア・カムチャツカ半島付近を震源とする地震で出された。遠くから何度も到達する「遠地津波」だったため、住民は揺れを感じないまま高台への避難が求められたほか、しばらく自宅に帰ることができない状況が続いた。折からの猛暑で、避難所を開設した自治体からは熱中症予防に必要な物資が足りなかったとの反省の声が上がった。
避難所は従来から暑さ、寒さへの対策を講じることになっていたが、冷暖房などの施設整備面に偏っていた。今回の改定では、塩分や水分を補給できる物資の確保などを盛り込む予定だ。県は、専門家の助言を得ながら、停電などで冷房機器が使えない場合でも対応できるような避難所の備蓄品の在り方を協議してほしい。
7月の津波警報を巡る対応では、屋外や避難所ではない場所に避難した人も少なくなかった。気候変動による洪水の多発などを背景に、警報が出されればすぐに身の安全を確保できる場所に逃れるという行動が定着した表れともいえる。その半面、それぞれの場所に避難した住民をどのように支援するかが課題となっている。
県は、マニュアルの改定を通じて、避難所以外に避難した人の確認方法や、円滑な避難所への誘導の手順を定める。大規模な災害が発生した場合には、普段使っている通信網が途絶することも想定される。行政と地域防災組織の人的な連携、非常用の通信機器の配備などを組み合わせた安否確認や安全確保の体制構築が求められる。
避難所を巡っては、国が昨年12月、「スフィア」と呼ばれる国際基準に基づき1人当たり最低3・5平方メートルの専有スペース、災害初期段階で50人に1基のトイレを確保するよう指針を改定した。しかし、共同通信社の調査では、トイレ数は県内の32市町村、居住空間は27市町村が「基準を満たしていない」と答えているのが現状だ。
トイレや居住空間の確保は、避難後の「災害関連死」やエコノミークラス症候群を防ぐために重要な取り組みだ。県と各市町村は、現在指定している避難所の改修に加え、可搬型の清潔なトイレや新たな避難場所の確保などの努力を継続してもらいたい。