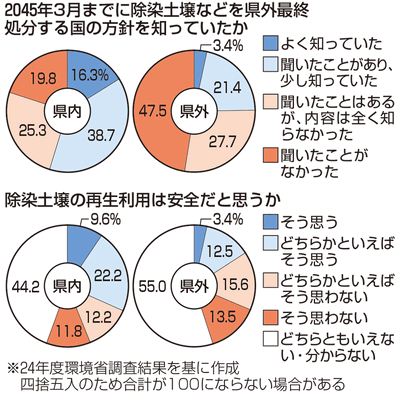「なぜわざわざ汚染土を全国にばらまくのか」
「最終処分場は福島に造るのが妥当だろ」
「地産地消でお願いします」
東京電力福島第1原発事故後の除染土壌に関する記事が載るたび、匿名のコメントがウェブ上にあふれる。中間貯蔵の開始から10年。県外最終処分の「約束」は、知らない人の方が圧倒的に多い。
環境省の本年度調査によると、2045年3月までの県外最終処分が法定化されていることを「知っている」と答えた県外在住者は24.8%。7年間ほぼ横ばいで推移し、4人中3人は「全く知らない」「聞いたことがない」と回答した。
1キロ当たり8000ベクレル以下の土壌について、道路などに再生利用する政府方針を「知っている」はわずか13.4%。「安全だと思う」は15.9%、「家の近くで実施されてもいい」は21.0%だった。いずれの肯定的回答も7年間横ばいか、よくて微増にとどまる。
理解醸成策を探る同省の検討会座長の高村昇長崎大教授は「事故は関東に電力を送っていた原発で起き、今も古里に帰れない人がいる。最終処分は決して福島だけの問題ではない」と指摘。「再生利用や8000ベクレルの数字などの意味を理解し、判断できる環境づくりが必要だ。今のままでは『何となく怖い』と冷静な議論ができない」と語る。
政府は16年、本年度を期限とする全国的な理解醸成の戦略を描いた。21年度からは活動を強化し、東京や名古屋など7都市計9回の対話集会を開催。中間貯蔵施設(大熊町、双葉町)の視察会にも力を入れ、6年間で県内外から約2万2000人が足を運んだとされる。
効果を検証すると、参加者同士の対話を組み合わせた場合、再生利用に前向きな意見を持つ人が明らかに増えた。
同省は「社会の中心世代を担う」として若者に焦点を当て、25年度以降、対話活動を積極的に取り入れる。屋外広告や交流サイト(SNS)などを用いた広報も強化。残り20年で理解と共感を広げ、再生利用や最終処分場を受け入れる社会的機運を高める道筋を描く。
一方、歳月を経て風化は進む。原発事故の記憶のない世代が増え、高校生の7割は第1原発の電力が全て首都圏に送られていたことを知らない。
「風化は理解醸成にマイナスに働く」。東日本大震災・原子力災害伝承館長も兼ねる高村氏は、現状に危機感を抱く。
「だからこそ、福島の今を発信し続けなければならない。私たち一人一人に何ができるか考えてもらうことが非常に重要だ」