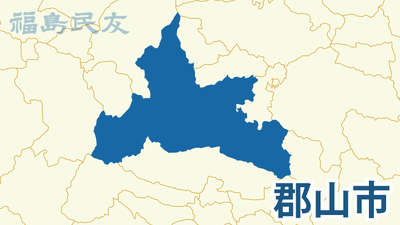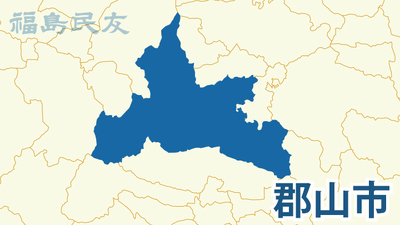県民1人が2023年度に出した1日当たりのごみの量は968グラムで、都道府県別で全国ワースト2位だった。ごみの排出量が多いと収集や焼却に伴うコストが増大するほか、最終処分場の容量の逼迫(ひっぱく)が早まることにもつながる。行政と住民が連携し、着実に排出量を減らすことが求められる。
ごみの排出量は、環境省の調査で毎年公表される。本県は東日本大震災前は全国平均とほぼ同じ水準だったが、震災後に排出量が急増しワースト1~3位で推移してきた。ただ、排出量は全国的に減少傾向にあり、本県もようやく震災後初めて千グラムを切り、震災前の10年度の985グラムも下回った。
県が排出量削減のため、ごみの大半を占める生活ごみを分析したところ、3割超が家庭から出た生ごみだった。生ごみは水分が多く、乾燥させるだけで重量を2割減らすことができる。各家庭が「生ごみの水きり」「料理の食べきり」「食材の使いきり」の三つの「きり」を心がけ、生活の中からごみを減らす環境づくりを進めていくことが重要だ。
排出量は家庭などの生活系のごみのほか、会社などの事業系のごみも合わせて算出される。事業系のごみの中で、最も多い割合を占めるのが事務所から出る紙ごみだ。紙ごみは、市町村に可燃物として回収を求めるとごみになってしまうが、きちんと分別してリサイクル業者に引き渡せば、ごみの排出量には計上されない。
県は本年度から、紙ごみ削減に向け、廃コピー用紙を2千キロ以上リサイクルする事業者を対象に費用の一部を補助する制度を設けた。環境に配慮した経営は、持続可能な開発目標(SDGs)の観点からも評価に値する取り組みだ。各企業は事業系ごみの積極的なリサイクルを進め、ごみ排出量の削減と資源の再利用の両立を図ってもらいたい。
22~23年度に100グラム以上の削減に成功した県内の自治体では、毎月の広報でごみの量や分別方法を繰り返し掲載するなどの啓発を進めている。また、相馬市などでは、リユース会社と協定を結び、各家庭で不要になった家具などを業者に引き取ってもらう機会を設ける取り組みも出ている。
県によれば、市町村はそれぞれごみの削減を進めているが、横の連携はなかったという。そのため、昨年度に全市町村で構成する「ごみ減量市町村連携推進会議」を設立し、取り組みの情報共有を始めた。県と市町村は、効果があった施策を積極的に水平展開し、ごみの総量抑制に努めてほしい。