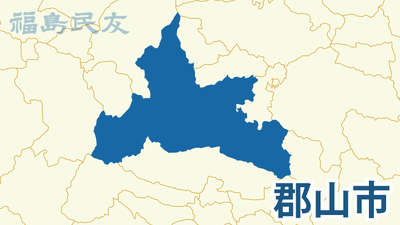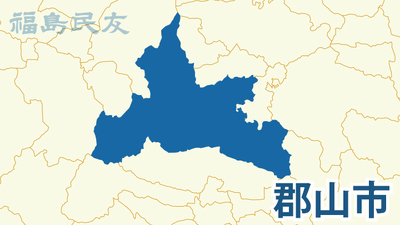本県はがんや心疾患、脳血管疾患など、生活習慣が発症に大きく影響するとされる病気で亡くなる人の割合がほかの県などより高い。病気の要因となる生活習慣を改善することで、より健やかな生活が送れるようにしたい。
厚生労働省が公表した2024年人口動態統計(概数)によると、本県の死因別死亡率(人口10万人当たりの死亡数)は脳血管疾患で121・9人(前年127・1人)、糖尿病17・7人(同19・1人)とやや改善した。都道府県別で前年のいずれもワースト4位から、脳血管疾患は5位、糖尿病は6位となった。がんや心疾患の死亡率も下がった。
県は東日本大震災後の肥満傾向の悪化などを受けて、健康増進を促す施策に力を入れてきた。健康づくりは一朝一夕にはいかないことを考慮すれば、わずかではあるものの改善が見えたのはよい兆候だ。ただ、全国的にみれば、生活習慣病で亡くなる人の割合は依然高いことに変わりはない。県などは引き続き予防の取り組みを強化する必要がある。
県の2035年までの健康施策の計画では、生活習慣病予防に向け、「減塩、禁煙、脱肥満」をスローガンに掲げた。塩分過多、喫煙、肥満はいずれも生活習慣病との関連性が強い要素だ。
本県は1日当たりの塩分摂取量が平均を4グラム上回り、特定健診でメタボリックシンドロームと診断された人の割合も高い。喫煙率については全国平均を5ポイント上回っており、全国ワーストだ。これでは、生活習慣病にかかる人が多いのは当然だろう。
県などは、民間企業との減塩推進組織の設置、希望する妊婦やその家族への禁煙補助薬の送付、スマートフォンのアプリを使ったウオーキング促進などの施策を展開している。ただ、こうした施策は、自らの健康に関心を持ち、積極的にその保持に取り組もうとしていることが前提となるのが大きな課題だ。
県やそれぞれの住民の健康保持を担う市町村が注力すべきは、健康にあまり関心がない層を減らすことだろう。例えば、県は健康に関するイベントで、テレビのキャラクターショーを開催するなどして、必ずしも健康への関心が強くない層を呼び込もうとしている。
こうした取り組みに加えて、働く人が一日のうち多くの時間を過ごす職場を通じて日頃からの運動を促すなどして、健康に関心を持ってもらうきっかけを増やすことが重要だ。行政はさらに知恵を絞ってもらいたい。