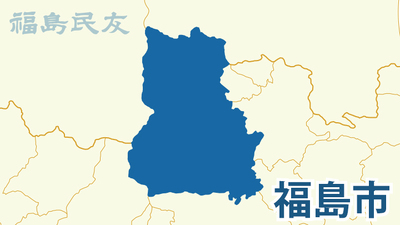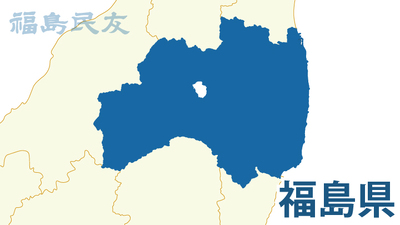政府は賃上げを求めるだけでなく、持続的な賃上げが可能になるよう、中小企業の経営基盤の強化を後押しすべきだ。
福島地方最低賃金審議会は本県の最低賃金(時給)を現行から78円引き上げ、1033円にするよう福島労働局に答申した。厚生労働相の諮問機関、中央最低賃金審議会が示した目安額に15円上乗せした。引き上げ幅は過去最大で、答申額は初めて1000円を超えた。
全都道府県のうち、39道府県で国の示した目安額を超えている。最低賃金の低い東北、九州などで大幅な上乗せが相次いだ。本県でも物価の上昇に賃上げが追い付かず、家計のやりくりに苦労している人は少なくない。他県と同様に国の目安を上回った本県の答申額は妥当な水準といえよう。
本県の最低賃金の適用時期は例年10~11月だが、今回は企業側に準備期間が必要だとして、来年1月1日となった。最低賃金の引き上げは労働者の生活改善に資する部分があるものの、体力の弱い小規模企業などには大きな負担だ。
全体の労務費を維持するため人員を減らし、1人当たりの負担が増えるようになれば、労働者にとって逆効果でしかない。最低賃金の引き上げは、より賃金の高い地域や企業への人材流出を防ぐ狙いもある。各企業は業務の見直しやコスト削減などを徹底し、人件費の捻出に努めてもらいたい。
政府は2020年代中に最低賃金を1500円に引き上げるという壮大な目標を掲げる。最近の物価上昇の動きと、日本の最低賃金が国際的に低水準にあることを踏まえれば自然の流れだが、企業が業務の効率化、設備投資などで大幅に生産性を向上させなければ、実現は到底困難であろう。
石破茂首相は、中小企業の設備投資などへの助成金の対象拡大、補助金の要件緩和を行う方針を示した。政府は即効性のある支援策を早急にまとめ、県などと企業に取り組みを促す必要がある。
人件費などのコスト上昇分を商品やサービスの価格に反映させることも重要だ。政府の調査によると、中小企業が上昇分を価格に反映した割合を示す「価格転嫁率」のうち労務費の転嫁率は、原材料費に比べて低い水準にある。サプライチェーン(供給網)では下請けの段階が1次から2次、3次となるほど転嫁率が下がっていた。
来年1月に施行される改正下請法は、発注者側の一方的な代金決定の禁止などが追加され、適正な価格交渉の促進を図る。政府は改正法を周知し、企業間の価格交渉の監視などを強化してほしい。