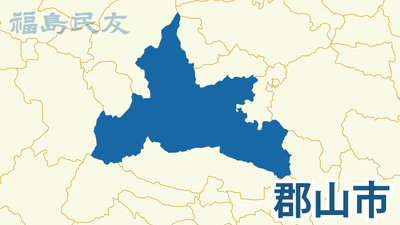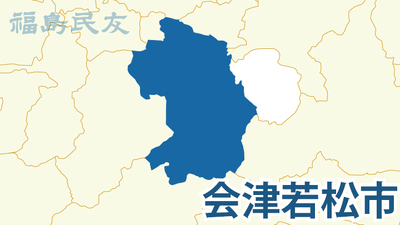県議会で、本県農業の方向性を規定する「県農業・農村振興条例」の改正案が審議されている。国の食料安全保障を重視した法改正を受けた対応で、議会最終日での可決が見込まれる。県は条例の理念に基づき、農林水産業振興計画を見直す。県民に良質な食料を供給できるよう、持続可能な農業の実現につなげる必要がある。
食料安全保障は、ロシアのウクライナ侵攻などによる世界の食料需給の変動を見越し、国内での農業生産や非常時の輸入相手国の多様化などを図っていく施策だ。今回の条例改正では、県レベルで取り組むことができる対応として、県産農産物の安定生産の確保や環境との調和がとれた農業を強化していくことを求めた。
生産者の高齢化や遊休農地の解消が課題になっているため、改正案では、営農可能な土地を地域の主要な担い手に耕作してもらう農地集積を進めることを新たに位置付けた。県内の農地集積率は、昨年度の段階で4割強にとどまる。県は、コメの増産や輸入に頼りがちな飼料用作物などの生産に対応するためにも、優良な農地を意欲ある生産者につなぐ取り組みを進めていくことが重要だ。
気候変動などへの対応も盛り込んだ。農業経営の安定に不可欠な要素として、家畜の伝染病や作物に有害な動植物の発生を予防することを記した。イノシシなどによる農産物の食害については、新たに条文を設け農地への侵入防止対策などの必要性を強調した。
気温の上昇や野生動物の生息域拡大は、生産者個人の努力では解決できない問題だ。近年では、わずかな断片からでも再生し農地や水路などを覆ってしまう、南米原産の植物が県内で発見された事例もある。県と農業生産団体、市町村が連携し、地域単位で最新の知見の共有や被害を軽減する対策を講じる体制を整えてもらいたい。
東京電力福島第1原発事故を巡る農産物の放射性物質の検査については、これまで「検査体制のさらなる強化促進」を目標にしていた。しかし、事故から14年が経過し、国が定めた放射性物質の基準値を超えるような作物は出ていない。このため、改正案では「県産農産物の安全性を確保するための検査」を展開するよう書き換えた。
これまでの農業復興政策は、風評被害の払拭が大きな柱となってきた。県は今後、安全性が十分に担保されていることを前提に、作物ごとのさらなる品質向上や市場に求められる数量の確保などを進め、震災前の販路を取り戻していく施策を打ち出してほしい。