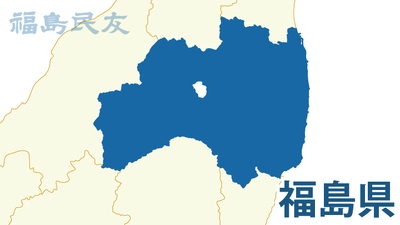規範意識や責任感の欠如が招いた事態だ。職員の意識改革や業務の改善を急ぐ必要がある。
日本郵便が配達員の酒気帯びの有無を確認する点呼を適切に実施していなかった問題で、国土交通省は貨物自動車運送事業法に基づき、全国の111郵便局にある軽バン計188台を15~160日間の使用停止とする行政処分を通知した。県内では須賀川、会津若松両郵便局が処分対象で、それぞれ3台が20日間の使用停止となる。
日本郵便は6月にも大型のトラックやバン約2500台について貨物運送事業許可の5年間の取り消し処分を受けている。今回の軽バンの処分は第1弾だ。国交省は今後も法令違反が確認された郵便局を順次処分する方針で、最大で約2千局に広がる可能性もある。
日本郵便は他社への委託や近隣の郵便局の応援で対処する構えだが、今後、年末年始の繁忙期とも重なり、処分台数が増えれば物流業界全体への影響が懸念される。日本郵便には、全国に張り巡らされた物流網に混乱が生じないよう万全な対応を求めたい。
日本郵便で発覚した問題は不適切な点呼だけでない。総務省は先月、郵便物を配達できなかった場合の対外公表の基準が不適切だとして、改善を求めて行政指導を通知した。現在は郵便物を隠したり捨てたりするなど、郵便法に抵触する犯罪に当たる場合は公表しているが、故意や重大な過失がない紛失などは公表していない。
日本郵便はこれまで非公表案件でも警察や総務省に相談し、特定できた差出人に説明し謝罪をしてきたという。それ以外にも差出人が事態を把握せず、不利益を被っているケースがあるとみられる。不配達は言語道断であり、事実を差出人に伝えないのは理解できない対応だ。早急に基準を見直し、過去の非公表事案についても利用者への説明責任を果たすべきだ。
相次ぐ不祥事の根源として、組織全体でのモラル低下が指摘されている。不適切点呼問題以降も、通勤時の社員の酒気帯び運転などが相次いで判明している。小池信也社長は記者会見で再発防止策について「今は改善をみており、いかに定着させていくかが重要な課題だ」と語ったが、楽観できるような状況ではないのは明白だ。
メールや交流サイト(SNS)の普及で郵便離れが加速しているなか、人口減少が深刻な地域や中山間地域では郵便局が大きな役割を担っている。民営化されたとはいえ、その高い公共性を自覚して改革を進めなければ、失墜した信頼は取り戻せない。