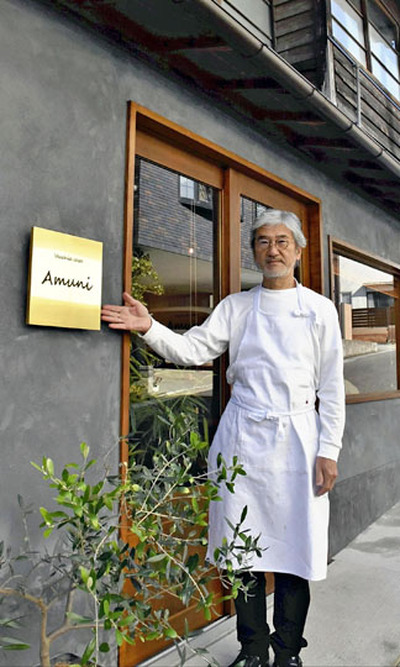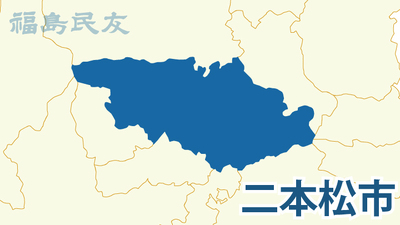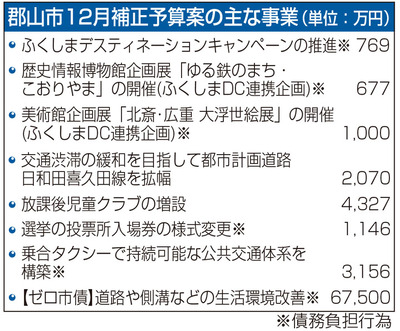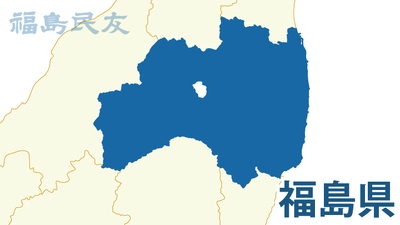今年のノーベル生理学・医学賞に、体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性T細胞」を発見した坂口志文(しもん)大阪大特任教授と米国の2氏が選ばれた。
坂口氏は、体を病気から守る免疫システムのうち、侵入した病原体などの異物と認識されたものを攻撃するT細胞の中に、過剰な攻撃が体に害を与えないよう、抑制する役割を担うものがあることを発見した。後に米国の2氏が見つけた遺伝子がこのT細胞の働きに重要と分かった。
制御性T細胞の働きを調整できれば、がんなどの治療に役立つと考えられている。3人の発見はアレルギーや自己免疫疾患などの治療、がん免疫療法、臓器移植後の拒絶反応に関する研究の土台となっている。関節リウマチや糖尿病など身近な病気の治療などにもつながる可能性がある。医療への貢献は極めて大きい。
坂口氏は1977年から所属した愛知県がんセンターで、過剰な免疫機能を抑える仕組みが体にはもともと備わっているのではないかとの着想を得て、日米の大学や研究所を転々としながら研究に取り組んだ。95年に制御性T細胞の目印となる分子を特定し、その8年後の細胞に関わる重要な遺伝子の特定につなげた。
坂口氏は制御性T細胞の存在を突き止めた後も、先に存在が提唱されたものの存在しないことが分かった細胞と同一視されて、論文を出しても正当な評価を受けられない時代が続いた。研究費の調達に苦労したこともあったという。そのような中、粘り強く研究に取り組み、命や健康を支える研究の発展につながる成果を生み出した坂口氏らの努力をたたえたい。
日本の科学者の受賞は数年おきに出ているが、今後もそれが続くのかは不透明だ。日本の科学者による研究論文の引用される回数が減少傾向にある。
今回の受賞で分かるのは、地道な研究を続け、大きな成果を生むには膨大な時間と費用、それを支える環境が必要ということだ。国が基礎研究を支えるために設けている科学研究費補助金は、研究テーマの有用性をアピールしないと獲得が難しく、補助の期間も短い。坂口氏のように、時間がかかり、必ずしも有用となるのか分からない研究を国内で行うのは難しくなっていく恐れがある。
国際社会の中で日本の強みの一つが、科学研究の分野だ。世界をリードする研究成果を生み続けるためにはどのような環境や制度を整えるべきか。受賞はそれを考える契機となる。