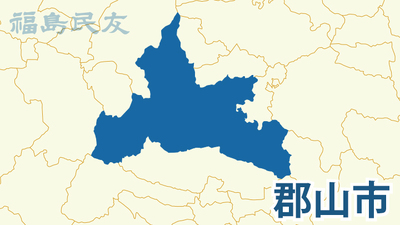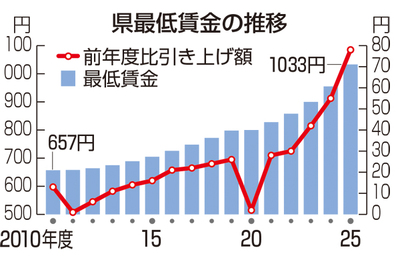猛暑の時期にたびたび渇水の懸念が話題に上る羽鳥ダム(天栄村)。ダムの水を利用する稲作農家には水不足の悩みがつきまとう。「だったら水をあまり使わない農法を」。鏡石、矢吹町の田んぼで今年、水を張らない節水型コメ作りの挑戦が始まった。これまでの常識を覆す新たな農法に、関係者は水不足問題の解消と作業の効率化、コスト削減に期待を込める。
羽鳥ダムを水源とする農業用水は、白河、須賀川、鏡石、矢吹、泉崎の5市町村の田んぼに供給されている。冬場の降雪量低下が影響し、ダムに流入する雪解け水が減ったことに加えて、猛暑と少雨が続く夏の時期は、渇水傾向となる。ダムの農業用水を管理する矢吹原土地改良区(矢吹町)の担当者は「羽鳥ダムの水不足は永遠の課題」と語る。
5日現時点でのダムの貯水率は44.2%。例年より少し多い水量が蓄えられているが、今月はコメ作りで最も水が必要な「出穂期」を迎えるため、貯水率の低下が懸念されている。
改良区は地域の課題を乗り越えようと、本年度から節水型水稲の試験栽培に乗り出し、改良区の組合員15人が挑戦している。
そのうちの一人が副理事長の佐藤幸一郎さん(77)。自身が所有する鏡石町桜岡地区の田んぼで作付けした。
改良区が取り入れた技法は最近、研究が進んでいる「節水型乾田直播(かんでんちょくは)栽培」。3カ月ほどかかる苗作りや、田んぼの代かき、水張り、田植えなどの初期作業は必要ない。耕した田んぼの乾いた土に直接、機械を使って種もみをまく。
佐藤さんは5月上旬ごろ、約45アールの田んぼに約1時間でコシヒカリの種をまいた。その後、走り水を加えて、2週間で発芽。種に付着させた菌根菌(きんこんきん)が作用し、土の中の水分や栄養を根に取り入れて、少ない水量での稲の生育が可能となる。佐藤さんは「従来の農法の10分の1程度の水量で稲が育ちそうだ」と語る。また田植えまでの作業工程と水の管理が減ることで「生産費も大幅に抑えられ、作業効率も上がる。少ない人手でコメを作ることができる」とメリットを並べた。
同改良区内では、水不足の影響でコメが育ちにくい環境となったことなどを理由に、ここ10年間で約270軒の農家が離農した。農家の高齢化と後継者不足が進む中、新たな農法は、生産性向上の切り札にもなりそうだ。担当者は「技術を確立させて、節水型乾田直播栽培の安定生産を目指したい」と意気込む。
◇
節水型乾田直播栽培 植物の根と共生して、植物の生育を助ける微生物「菌根菌」を使用することで、少ない水量で水稲の生育が可能となる。菌根菌が水稲の根に感染。細かい根はり構造を作りだし土壌の中の養分や水分をより多く吸収する。これにより、乾いた状態の田んぼに菌根菌を付着させた種をまき、芽が出たあとも水を張らずに稲を育てることができる。