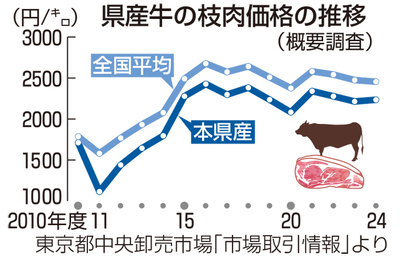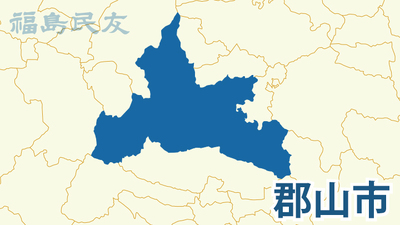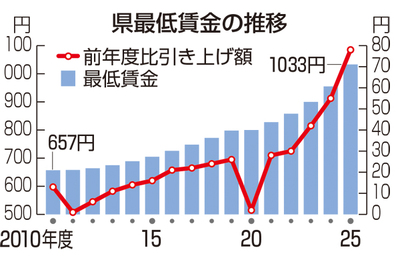新潟・福島豪雨で被災したJR只見線の全線再開から間もなく3年となる。施設の維持管理を県、運行をJR東日本が担う「上下分離方式」を採用した路線は今年、豪雪の被害もあり、一部区間で長期運休を余儀なくされた。老朽化した設備の安全対策なども予定される中、路線を守る人材の確保が課題となっている。
専門的な知識必要
奥会津の豊かな自然の中を鉄路が走る。「只見線は地域に愛される路線。ここでしかできないやりがいがある」。只見線の維持管理を担当する県只見線管理事務所の菊地悠介さん(32)は思いを語る。
2022年10月1日に運行を再開した会津川口―只見間は、県が施設の維持管理を担い、県と沿線の17市町村が維持費を負担。安全な運行に向けて路線を守るのが、菊地さんら管理事務所の職員だ。
鉄道は線路や枕木、トンネルをはじめ、信号や電気設備など運行に必要な設備が多岐にわたり、維持管理を担う技術者には多くの専門的な知識が求められる。
現在、維持管理に当たるのはJR東日本からの派遣職員や、菊地さんら県土木部の技術者、利活用を進める事務方を含め計11人。ただ、27年秋にはその中心を担ってきたJR東からの職員派遣が終了する予定で、自前の技術者確保が急務となっている。
採用基準を緩和
人材確保に向け県は今年7月、技術者の採用を始めた。だが、3人程度の募集に対し、応募はわずか1人にとどまった。人手不足などを背景に技術者の採用は難しさを増しており、特に鉄道のような専門性の高い人材の確保はなおさらだ。
県生活交通課の担当者は「(技術者は)現在でもぎりぎりの状況。豪雨や雪崩など災害が起きれば、安定的な管理は難しくなる」と危機感を募らせる。
来年1月には国の認定を受けた鉄道事業再構築事業として、橋梁(きょうりょう)の老朽化対策工事を控えるなど、さらに人手が必要となる。こうした状況を受けて県は9日から、基準の経験年数を「5年以上」から「3年以上」に緩和するなど応募のハードルを下げ、技術者の再募集を始める方針だ。
進む沿線活性化
人口減少が進む会津で、10年以上の時を経て全線再開にこぎ着けた只見線は、地元にとってまさにシンボル的存在だ。金山町の馬場清次さん(79)は「踏切の音が畑に鳴り響くのが聞こえると安心する」と話す。全線開通から3年の節目に向けて、馬場さんは近隣住民と只見線を応援するための企画も練っており「只見線は地域にとってなくてはならない存在。列車に手を振るイベントなどを通してこれからも盛り上げていきたい」と意気込む。
只見線は台湾などからインバウンド(訪日客)を呼び込む観光資源としても注目が高まっており、沿線では全線再開を地域活性化につなげようと、官民を問わず、さまざまなアイデアで只見線を守るための取り組みが進む。
それだけに、専門的な技術で只見線を維持管理する人材の確保は不可欠だ。県只見線管理事務所の羽生宏史所長は、路線を守り続けるための心境を吐露する。「只見線は地元の思いを受けて復活した路線。『県職員として地元に貢献したい』という思いがある技術者に一緒に路線を担ってほしい」
◇
JR只見線 2011年7月の新潟・福島豪雨で甚大な被害を受け、会津川口―只見間が長期間不通となった。JR東日本が示した上下分離方式を導入して復旧し、22年10月に全線で再開通した。今年2月には会津を中心とした記録的大雪の影響を受け、2月4日から運休。除雪が完了した場所から順次運行を再開したが、最後まで運休していた会津川口―只見間が復旧したのは5月16日だった。