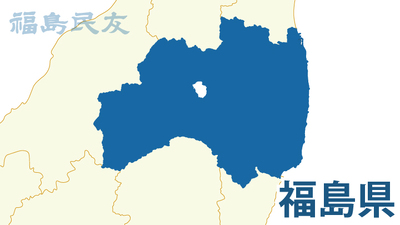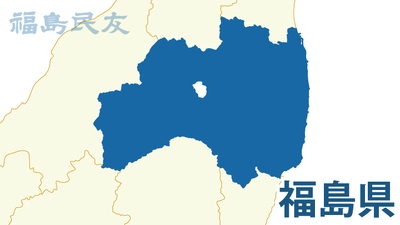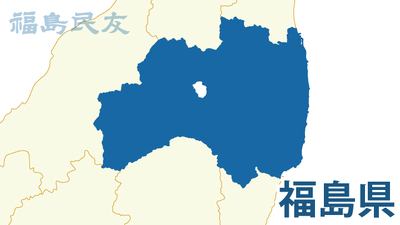県内の本年度の新規就農者数が391人で、調査を開始した1999年度以降で最多となった。生産者の高齢化などで農業生産の持続可能性が危ぶまれる中、就農者数が伸びているのは朗報といえる。県や市町村は、さらなる担い手の確保につながるよう、取り組みを強化していく必要がある。
本県の新規就農者数は東日本大震災以降、おおむね増加傾向にあり、2022年度からは4年連続で300人を超えている。本年度の新規就農者のうち、独立した農家として生産に取り組む自営就農は151人で、昨年度並みだった。農業法人などの従業員として働く雇用就農は、昨年度より4割増の240人で、過去最多を達成する大きな要因となった。
雇用就農は初期投資の負担がないことなどから、就農の入り口として人気があり、今後も伸びが期待される。県は、希望者が人材派遣会社に在籍し、給与を得ながら県内の農業法人で「お試し就農」する制度を設けている。昨年度は、利用者の8割が派遣先に就職する実績があった。県は制度の充実などを図り、農業を志す人を県内の農業法人に着実につないでいくことが重要だ。
新規就農者における雇用就農者は21年度以降、自営就農した人の数を上回るなど、新規就農者数を底上げしてきた。ただ、最初に就職した農業法人への定着率の低さが課題になっている。1年後の定着率は6割強、3年後は4割強で、5年後には2割にまで低下しているのが現状だ。
このため、県と県農業経営・就農支援センターは、労使間のギャップなどを解消しようと、専門家を派遣しての雇用環境や経営意識の改善指導、勤務する若手農業者のネットワークづくりに着手している。県や関係団体が連携し、働き手が他の農業関係者との交流を通じて生産技術や意欲を高め合い、農業に長く関わっていける環境を整えてほしい。
自営就農を巡っては、151人のうち約半数が農業関係の学校を卒業、あるいは他の業種を経験するなどした後、農地を家族などから受け継いで就農した人だ。残りの半数は、県内で農地を確保して、農業に新規参入してきた人たちになっている。
新規参入者の中には、県外から本県に移住して就農した人が含まれている。県は、首都圏での説明会に加え、本県に移住して農業に取り組むイメージを描けるような体験ツアーを組み合わせ、意欲ある就農希望者を県外から招く試みにも一層力を入れてもらいたい。